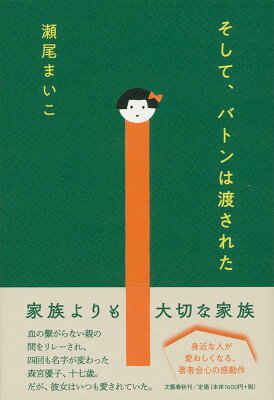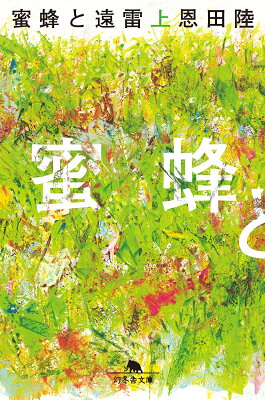どうも、読書中毒ブロガーのひろたつです。
日々読書に明け暮れ、面白い本を探すことに人生を注ぎ続けている私。そんな生粋の読書中毒である私が「これは最高だろ」と言える作品を集めた記事の第2弾である。
小説というのは、読んでみなければ面白いかどうか分からない。そして、読み終えるのには大体3時間ぐらいは取られてしまう。かなり効率が悪い。それだけの時間をかけて読んでみて「なんじゃこの糞小説は?!」となったら、目も当てられない。
皆様が少しでも効率よく、面白い小説にアクセスできるようお手伝いできれば幸いである。
では行ってみよう。
※第1弾はこちら。
101 いつか、虹の向こうに 著:伊岡瞬
尾木遼平、46歳、元刑事。ある事件がきっかけで職も妻も失ってしまった彼は、売りに出している家で、3人の居候と奇妙な同居生活を送っている。そんな彼のところに、家出中の少女が新たな居候として転がり込んできた。彼女は、皆を和ます陽気さと厄介ごとを併せて持ち込んでくれたのだった…。優しくも悲しき負け犬たちが起こす、ひとつの奇蹟。第25回横溝正史ミステリ大賞&テレビ東京賞、W受賞作。
抜群の筆力とリーダビリティで、ぐいぐい読ませる優秀ミステリー。デビュー作でこれって…伊岡瞬は優秀すぎる。みんなもっと伊岡瞬を絶賛しろ。
プロットは強固だし、会話は小気味よいし、ハラハラ・ドキドキは盛り込んであるしで、これさえあればいいっていうのが揃ってる。小説界のイオンみたいな作品。
けっこうキツイ描写で重い所もあるけれど、全体的にどこかオフビートで、思わずふっと吹き出してしまう瞬間がある。
102 なかよし小鳩組 著:荻原浩
倒産寸前の零細代理店・ユニバーサル広告社に大仕事が舞いこんだ。ところが、その中身はヤクザ小鳩組のイメージアップ戦略、というとんでもない代物。担当するハメになった、アル中でバツイチのコピーライター杉山のもとには、さらに別居中の娘まで転がりこんでくる。社の未来と父親としての意地を賭けて、杉山は走りだすが―。気持ちよく笑えて泣ける、痛快ユーモア小説。
荻原浩の真骨頂である笑いに特化した作品。
主人子は普通のオッサン。我々となんら変わりない一般人である。そんな彼が奮闘している姿は、温かい笑いと涙を誘う。これはなかなか素敵な読書体験なるはずだ。
それにしても、やっぱりこの人上手いわ。読者の心のツボを突くのが上手い。
疲れた身体と心によく効く、栄養剤のような作品です。
個別紹介記事⇒荻原浩の『なかよし小鳩組』は笑いと感動を両立させた稀有な作品
前作はこちら。荻原浩のデビュー作ということもあり、稚拙な部分は多少あるものの荻原浩の魅力は存分に発揮されているし、主人公も同じなので合わせてぜひ。
103 そして、バトンは渡された 著:瀬尾まいこ
森宮優子、十七歳。継父継母が変われば名字も変わる。だけどいつでも両親を愛し、愛されていた。この著者にしか描けない優しい物語。 「私には父親が三人、母親が二人いる。 家族の形態は、十七年間で七回も変わった。 でも、全然不幸ではないのだ。」 身近な人が愛おしくなる、著者会心の感動作
かなりトリッキーな設定の珍しい作品。地味な装丁も相まって、期待半分ぐらいで読んでみたのだが、これがまあ素晴らしい。不覚にも泣いちゃったよ。
描写や会話のいちいちに暖かさが満ちていて、読んだ人を幸せにしてくれる作品である。
青春を描いているので、読んでいて苦しくなる部分もあるが、それもまた作品の味わい深さである。存分に楽しんでもらいたい。
日々を忘れて心を軽やかにしてくれる、素晴らしい一冊。本屋大賞をかっさらったのも納得です。
104 竜が最後に帰る場所 著:恒川光太郎
しんと静まった真夜中を旅する怪しい集団。降りしきる雪の中、その集団に加わったぼくは、過去と現在を取り換えることになった―(「夜行の冬」)。古く湿った漁村から大都市の片隅、古代の南の島へと予想外の展開を繰り広げながら飛翔する五つの物語。日常と幻想の境界を往還し続ける鬼才による最重要短編集。
この面白さは未体験。書評ブロガーとしての役割を放棄するような発言になるけど、マジで面白さを表現する語彙がない。っていうか、この世界にまだ存在してないんじゃないだろうか。無理に表現するとするならば、「世にも奇妙な物語っぽい」かな…?
なので、この面白さを味わいたかったら読むしかない。恒川光太郎の作り出す、少し奇妙で、独特な浮遊感をもたらす読書体験は、他の作家では無理だ。
ありきたりなドラマとか、プロットで楽しませるタイプの作品ではないので、面白さが永遠に風化しないと思う。隠れた名作としてずっと愛されることだろう。
105 メドゥサ、鏡をごらん 著:井上夢人
作家・藤井陽造は、コンクリートを満たした木枠の中に全身を塗り固めて絶命していた。傍らには自筆で「メドゥサを見た」と記したメモが遺されており、娘とその婚約者は、異様な死の謎を解くため、藤井が死ぬ直前に書いていた原稿を探し始める。だが、何かがおかしい。次第に高まる恐怖。そして連鎖する怪死。
最強リーダビリティ作家井上夢人。この作家は恐ろしく読みやすいのが特徴で、文章がするすると脳内に入っていってしまう。人にイメージを伝えるすべを心得ているというか、手の平で踊らされているというか…。とにかく、上手い。
そんな読みやすい文章を繰り出す作家が、ホラー小説を書くとどうなるか…?
それは読んでからのお楽しみということで。
井上夢人って名前がすでに恐い度…☆×5
106 幕が上がる 著:平田オリザ
ある地方の高校演劇部を指導することになった女性教師が部員らに全国大会の出場を意識させる。高い目標を得た部員たちは恋や勉強よりも演劇ひとすじの日々に。演劇強豪校からの転入生に戸惑い、切磋琢磨して一つの台詞に葛藤する役者と演出家。彼女たちが到達した最終幕はどんな色模様になるのか。爽快感を呼ぶ青春小説の決定版!
どストレートに良い小説。気持ちよく読める青春モノ。でも他では見られない裏切りが用意してあるのがニクい。どんな裏切りかは読んでのお楽しみ。
ももクロ主演で映画化もされている。ちょっと観てみたけど、本作の魅力は毛ほども伝えていなかった。完全に別作品。ありゃダメだ。
青春ものの良さが全部入っているんだけど、ありきたりな展開は一切排除されているのが凄い。作者の性格の悪さが出てますな。うん、好きだよ。
107 クリス・クロス-混沌の魔王 著:高畑京一郎
MDB9000。コードネーム“ギガント”。日本が総力を結集して造り上げたスーパーコンピュータである。世界最高の機能を誇るこの巨大電子頭脳は、256人の同時プレイが可能な仮想現実型RPG「ダンジョントライアル」に投入された。その一般試写で現実さながらの仮想世界を堪能する参加者たち。しかし、彼らを待っていたのは華やかなエンディングではなく、身も凍るような恐怖だった…。第1回電撃ゲーム小説大賞で「金賞」を受賞した高畑京一郎が描き出す驚愕の仮想現実世界。日本初のバーチャルRPGノベルが、今、文庫で起動する―。
ずいぶんと昔の小説だが、仮想現実を題材にした傑作。そろそろ現実が追いつき始めたぐらい…かな?
これを書いている高畑京一郎は遅筆で有名。冨樫なんて相手にならないぐらい超遅筆。
しかし、遅筆作家あるあるの例にもれず、彼は面白い作品しか発表しないのだ。そこは偉い。そこしか偉くない。最新シリーズが終わることはきっとないのだろう。
そんな彼の衝撃のデビュー作である。偏見を持たずに読みたまえ。
時代先読み度…☆×5
108 モンスター 著:百田尚樹
田舎町で瀟洒なレストランを経営する絶世の美女・未帆。彼女の顔はかつて畸形的なまでに醜かった。周囲からバケモノ扱いされる悲惨な日々。思い悩んだ末にある事件を起こし、町を追われた 未帆は、整形手術に目覚め、莫大な金額をかけ完璧な美人に変身を遂げる。そのとき亡霊のように甦ってきたのは、ひとりの男への、狂おしいまでの情念だった——。
稀代のストーリーテラー百田尚樹による、整形をテーマにしたドロドロ小説。
見た目問題をエンタメとして昇華するために、かなり過剰な演出が盛り込まれているけれど、面白ければなんでもいいの好例。
というか、細けえことは置いていて、面白さでぶん殴れる百田尚樹はやっぱり凄い。どれだけ嫌われて叩かれようが、作家は面白いものを書ければ正義である。
実写映画化されてるらしいけれど、整形前のメイクは相当お寒い感じになってるんでしょうなぁ…。
“画”の強さを好き放題に描けるのは、やっぱり文章メディアの強み。
109 私の頭が正常であったなら 著:山白朝子
突然幽霊が見えるようになり日常を失った夫婦、首を失いながらも生き続ける奇妙な鶏、記憶を失くすことで未来予知をするカップル、書きたいものを失くしてしまった小説家、娘に対する愛情を失った母親、家族との思い出を失うことを恐れる男、元夫によって目の前で愛娘を亡くした女、そして事故で自らの命を失ってしまった少女。暗闇のなかにそっと灯りがともるような、おそろしくもうつくしい八つの“喪失”の物語。
絶妙な怖さと切なさを持った、味わい深いホラー短編集。
ホラーとは言うものの、怖がらせることを全面に出しているわけではなくて、物語のエッセンスにほんの数滴垂らされてる程度。
軽い文章なのに、どこから胸をぎゅっと締め付けてくるような切なさがある。奇妙な話なんだけど、ほんのりと救われるような温かさがある。
私は小説をオススメするかどうかを決めるときに、「その作品でしか味わえないものがあるか?」を条件としているのだが、この作品はまさに、である。
心に染み込むような、怖くも優しく温かい物語。ゆっくりと味わってほしい。
個人的に、2018年に読んだ本ベスト1位の作品である。
→ 読書中毒ブロガーが2018年に読んだ年間ベスト10冊を発表する
110 海賊島事件 著:上遠野浩平
海賊。―それは常に奪う側に立ち、奪われる側には決して立たぬ者。魔法が文明を支配する世界の中で、海賊ムガンドゥ一族に略奪される危機が訪れる。全面戦争も辞さぬ強大な魔導艦隊が彼らに要求するもの、それは完全密室の中で起きた殺人事件の容疑者だった―全世界が緊張する中で海賊は一人の女を呼ぶ。その名はレーゼ・リスカッセ。そして彼女には、仮面を付けたとても奇妙な友人がいて―この世で最も美しい死体と、三代に亘る一族の歴史をめぐる因果の先に待つものは、勝利か敗北か、それとも―。
これは入れようかどうか迷ったんだよなぁ。
いや、面白いのは間違いない。保証しよう。ただ、前作を読んでおかないと、面白さが半減してしまうので、それが不安だったのだ。ただそれだけ。
きめ細かい設定と、繰り広げられる話の展開にめちゃくちゃ興奮したし、ニヤケが止まんなかったよね、実際。傍から見たら完全にイッちゃってる人だったと思う。誰にも見られてなくて本当に良かった。
特にクライマックスのシーンは垂涎モノ。オマージュに溢れたラスト一行も大好き。必読。(注:私は上遠野浩平の熱狂的なファンである)
こちらが前作。超好き。愛してる。
111 陰の季節 著:横山秀夫
警察一家の要となる人事担当の二渡真治は、天下り先ポストに固執する大物OBの説得にあたる。にべもなく撥ねつけられた二渡が周囲を探るうち、ある未解決事件が浮かび上がってきた…。「まったく新しい警察小説の誕生!」と選考委員の激賞を浴びた第5回松本清張賞受賞作を表題作とするD県警シリーズ第1弾。
この人、心理描写ウマすぎ。こんなの絶対に面白いでしょ。
警察小説なのに刑事が出てこないという異例の構成。それがまた面白いんだから驚き。花形の部署じゃないからこその苦悩や葛藤を、これでもかってぐらいにリアルに描き出している。
そして最大の魅力は短編としての切れ味!破壊力で言ったらこの記事で紹介している本の中でもトップクラス。横山秀夫は凄すぎる。
松本清張賞選考委員たちがうなるのも当然な珠玉の作品集である。超大好き。超オススメ。
個別紹介記事⇒全ての謎は人の心から生まれる。横山秀夫『陰の季節』
112 白夜行 著:東野圭吾
1973年、大阪の廃墟ビルで一人の質屋が殺された。容疑者は次々に浮かぶが、結局、事件は迷宮入りする。被害者の息子・桐原亮司と、「容疑者」の娘・西本雪穂―暗い眼をした少年と、並外れて美しい少女は、その後、全く別々の道を歩んで行く。二人の周囲に見え隠れする、幾つもの恐るべき犯罪。だが、何も「証拠」はない。そして十九年…。息詰まる精緻な構成と、叙事詩的スケール。心を失った人間の悲劇を描く、傑作ミステリー長篇。
この作品の魅力は非常に言葉にしにくいなぁ…。なんだろう?雰囲気?センス?キャラクター?
全編を通じて不穏な空気がずっと付きまとってくるのだが、それがなんとも不思議な読書感覚を私たちに与える。気持ちよくて、読み進まずにはいられないというか…。
ダメだ。私の拙い語彙ではこの作品の魅力を億分の一も伝えられん!とにかくめちゃくちゃ売れたから、買って損はない!←適当
個別紹介記事⇒小説界の蹂躙者である東野圭吾の真骨頂。『白夜行』
113 蜜蜂と遠雷 著:恩田陸
近年その覇者が音楽界の寵児となる芳ヶ江国際ピアノコンクール。 自宅に楽器を持たない少年・風間塵16歳。 かつて天才少女としてデビューしながら突然の母の死以来、弾けなくなった栄伝亜夜20歳。 楽器店勤務のサラリーマン・高島明石28歳。 完璧な技術と音楽性の優勝候補マサル19歳。 天才たちによる、競争という名の自らとの闘い。 その火蓋が切られた。
「文字から音楽が聴こえる」
と話題の名作である。音楽小説を語る上でいつの間にやら外せない作品になってしまった。直木賞と本屋大賞を同時にとった唯一の作品は伊達じゃねえってか。(2022年4月時点)
この作品の凄さは、音楽が聴こえるだけではなくて、登場人物たちのドラマパートにそこまで紙幅を費やしていなくて、演奏シーンが主たるものになっているのだけど、それでも読者をグイグイと読ませてしまうところである。
まさか音楽を描いた小説でここまで興奮できるとは思わなんだ。凄いとは聞いていたけど、予想を遥かに超えて楽しめた傑作である。
個別紹介記事⇒『蜜蜂と遠雷』の凄さを解剖してみる
114 誘拐 著:五十嵐貴久
歴史的な条約締結のため、韓国大統領が来日する。警察が威信をかけてその警護にあたる中、事件は起きた。現職総理大臣の孫が誘拐されたのだ。“市民”を通じて出された要求は、条約締結の中止と身代金30億円。比類なき頭脳犯の完璧な計画に、捜査は難航する―。鮮やかなラストに驚愕必至のクライム・ヒューマンサスペンス。
犯罪小説の中でも作家の腕が非常に試されるのが誘拐小説である。
数ある誘拐小説の中でも五十嵐貴久の『誘拐』は完成度では抜きん出た傑作だ。犯人側も警察側も、政府側も、全員がちゃんと仕事をしている。実はこれが非常に重要で、どれかひとつをバカにしておけば、物語運びは非常にラクになるのだ。でも五十嵐貴久はそうしなかった。全員を等しく、扱った。だからこそこんなに面白い。
よくぞここまで練り上げたと作者に拍手を贈りたい。
しかもそれだけの犯罪小説なのに、最後は爽快感でいっぱいになるしで、至れり尽くせりの作品である。いやー、本当に五十嵐貴久は賢い。
個別紹介記事→作者が緻密に組み上げた最強の犯罪小説。五十嵐貴久『誘拐』
115 ぼくらは虚空に夜を視る 著:上遠野浩平
…を再装填せよ、コアを再装填せよ、コアを再装填せよ。下駄箱に入っていた手紙に書かれたその無数の文字を視た瞬間、“普通の高校生”工藤兵吾は知ってしまう。今いる世界が“作られた世界”であることを。自らが人類史上始まって以来の“戦闘の天才”であることを。そして、超光速機動戦闘機「夜を視るもの」を駆り、虚空牙と呼ばれる人類の“敵”と闘う運命にあることを―!上遠野浩平が描く青春SFの金字塔、“ナイトウォッチ”シリーズ第一弾。
ちょっと毛色を変えて、ライトノベル作家から。
私が大ファンの上遠野浩平である。世界で一番好きな作家だ。いち読者である私だけではなく、同業者からも愛されており、彼に影響を受けた作家は数知れない。
ライトノベル作家だからと舐めてかからないでほしい。特にこの『ぼくらは虚空に夜を視る』は抜きん出た作品である。
彼がこの作品を発表したあと、日本のSFファンが「ライトノベル作家がこんなハイレベルなSFを書けるなんて…!」と驚いたというエピソードがあるくらいだ。
上遠野浩平は人智を越えた存在を描くのが非常に上手い作家である。
作中で出てくる”虚空牙”と呼ばれる人類の敵との対話は、神の存在を感じさせ、ゾクゾクする。
個別紹介記事⇒至高の設定チラリズム。上遠野浩平『ぼくらは虚空に夜を視る』
116 ぼくの、マシン 著:アンソロジー
00年代(西暦2000年~2009年)の10年間に国内で発表されたSF短篇から、歴史に残る作品をよりすぐった傑作選。
ちょっと毛色を変えてアンソロジーである。
まず皆さんにひとつ謝らなければなりません。私はこの作品の中で上遠野浩平による『鉄仮面をめぐる論議』しか読んでいません。なのに偉そうに紹介なんかして申し訳ない。
この本を語る権利がないそんな私だが、この『鉄仮面をめぐる論議』は絶対に外せない作品だと思っている。正直な話、今まで読んできた物語の中で一番好きである。超個人的な好みなのは百も承知。でも言わずにはいられない。
上遠野浩平の小説は「最高に興奮する」とか「どんでん返し」とか、そういった分かりやすい面白さは残念ながらない。言うならば「深み」である。
『鉄仮面をめぐる論議』という、この短い物語の奥の奥までを読者に感じさせる。それが脳みその芯を刺激してくるのだ。意味が伝わるだろうか。いや、こんな支離滅裂な文章で伝わるはずもない。
それにしても、一個の短編を紹介するために、どんだけ書くんだよって話だ。これが私の溢れんばかりの情熱だと解釈してもらえると助かる。そして誰か介錯してくれ。文章が止まらない。
上遠野浩平が好きな方は必見の傑作である。短編だが、彼の魅力が凝縮されていて大満足し、それと同時に物足りなさを覚えるという、相反する感覚を得ることだろう。
先に『僕らは虚空に夜を視る』を読んでおいてもらうと更に楽しめます。
117 たけまる文庫 謎の巻 著:我孫子武丸
業界初(のはず)の話題(のはず)の個人文庫、第二回配本分にして堂々の完結巻はミステリ短編を集めた「謎の巻」です。ファンおなじみの速水三兄妹のあいかわらずの推理が冴える「裏庭の死体」。2017年の東京湾を舞台に、ある有名な刑事の決死の活躍を描く「バベルの塔の犯罪」。自分自身の行動調査を探偵に依頼する不思議な中年男「青い鳥を探せ」など傑作八編。
せっかくなのでが世に知られていない作品を紹介した方が、記事としての価値が増すだろうし、皆さんもそういう情報を求めているはずだ。
この作品は我孫子武丸が才能を炸裂させていた頃、脂が乗りまくっていた時期の作品である。『かまいたちの夜』を出したのもこの頃。天才とはある人物の一時期を指すことが多いが、我孫子武丸の天才期はまさにこの頃だ。
短編集だが、ひとつひとつの破壊力が素晴らしいので選出させてもらった。古本屋でもなかなかお目にかかれない作品である。
118 怒り 著:吉田修一
殺人事件から1年後の夏。房総の漁港で暮らす洋平・愛子親子の前に田代が現われ、大手企業に勤めるゲイの優馬は新宿のサウナで直人と出会い、母と沖縄の離島へ引っ越した女子高生・泉は田中と知り合う。それぞれに前歴不詳の3人の男…。惨殺現場に残された「怒」の血文字。整形をして逃亡を続ける犯人・山神一也はどこにいるのか?『悪人』から7年、吉田修一の新たなる代表作!
ミステリーの手法を存分に使いながら、人間の心を克明に描き出した作品。群像劇とミステリーの相性はやっぱりいい。こういう手法を使う作品に、ハズレはあまり見かけない気がする。その分、作者も大変だと思うけど。盛り上げ方とか。
印象的なタイトルの意味は実はあまり重要ではなく、むしろ「悲しみ」の方が作品のテーマとしては近いかもしれない。それでも作者がタイトルに『怒り』を持ってきたのは、理由があるはず。…ただ単に出版戦術的に選んだだけかもしれんが。
けっこう重めの作品なので、ガツンとしたのが読みたい方はぜひ。
個別紹介記事⇒単純な物語に飽き飽きした人に贈る。吉田修一『怒り』
以上。新たな作品を見つけ次第、随時更新させていただく。