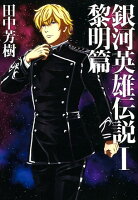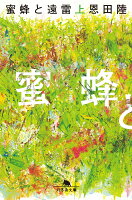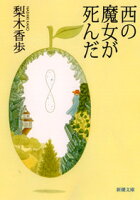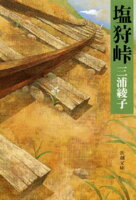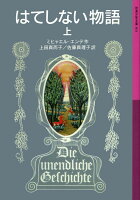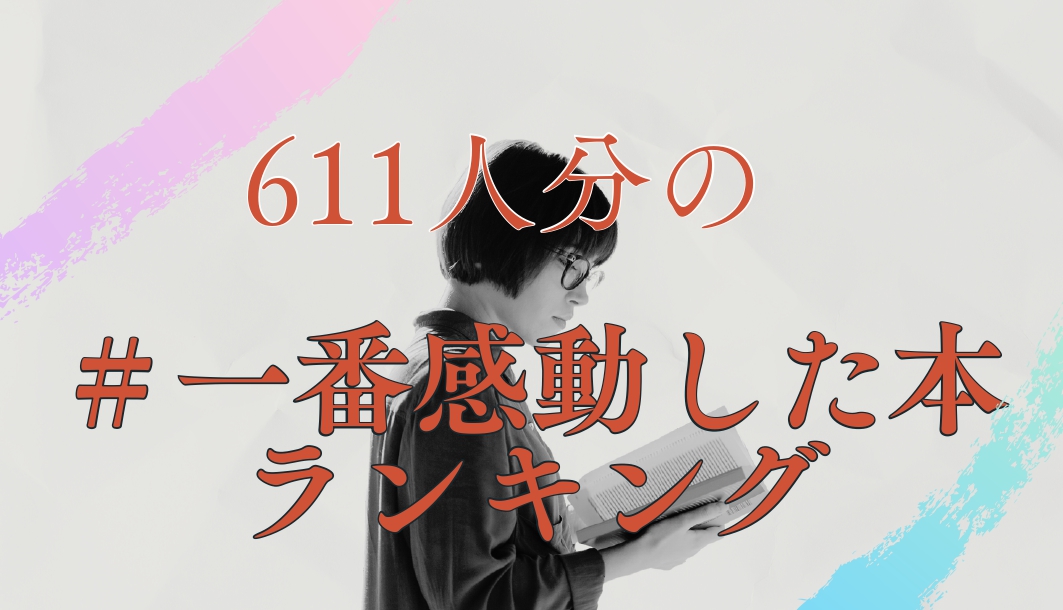
どうも、読書中毒ブロガーのひろたつです。筋トレすると、筋肉が付く前に関節を痛めるタイプです。関節が一生反抗期で困る。ういやつめ。
さて私の老化についてはどうでもいいとして、今回は読書仲間が大バズリしたタグに便乗した企画である。
売れないブロガーなのでこういう卑怯な真似をしないと生きていない時代なので、どうか あすなろ氏(@readingmaururer)はこんな矮小な私を寛大な心で許してやってほしい。今生で徳を積める大チャンスですよ!
ちなみにきっかけになったポストはこちら。
#一番感動した本
— あすなろ (@readingmaururer) 2025年4月8日
ストレートに訊きます
あなたが今まで読んだ中で一番感動した本は何ですか?
感動と言ってもいろいろある。
「涙が止まらなかった」
「首がもげるほど賛同して頷いた」
喜怒哀楽何でも結構。
感動とは心が動くこと。
あなたの心のいちばん中心に刺さっている本を紹介してください。
たまに大バズリする氏だけど、今回の規模は過去最大かもしれない。
それだけみんな感動した作品を布教したいし、そもそも感動に飢えているのかもしれない。世知辛えことばっかだからな、人生は。関節を中心に。
ということで、今回はこちらのポストで使用されたタグ #一番感動した本 で投稿されたものをいつも通り手作業で集計し、ランキングにこしらえたものである。
で、集計して意外だったのだが、とんでもないバズり方をした割に集まった作品数はそこまで多くなかった。
作品を挙げる人よりも圧倒的に「感動できる作品が知りたい」と思った人がいいねをしたりリツイートしている傾向である。
なので今回のランキングは、いつもみたいに「第50位!」みたいなことにはならない。
かなりぎゅっとしたランキングになっているし、同時ランクインばかりである。もしかしたらこのランキング結果を見て「全然ランキングの意味ねーじゃん」と思われる方もいるかもしれない。
だが、いち読書好きとして言わせてもらいたい。
「#一番感動した本」という、非常にポピュラーな縛りになっている今回。普段読書をしない層にめちゃくちゃ有用なランキングだと思う。
となると読書好きとしては、ここぞとばかりに大量の作品をオススメしたくなるのが性である。これが一番感動できる本ベスト10でっせ!!とか言いながら、50冊ぐらい押し付けたい。感動を暴力的に提供したい。好きと暴走は相性抜群である。そして暴走と嫌われは常にセット。つまり何かを好きになると、何かから嫌われるのである。これが真理。ちなみにオッサンになると、何もしなくても勝手に嫌われが発生していく。悲しい。何の話だっけ?老化?
とにかく今回のランキングは、とっつきやすい名作揃いである。
感動を効率よく摂取する一助にしていただけると助かる。もちろん皆さんが、という意味である。
それではランキングに行ってみよう!
8位
まずは2票を獲得した第8位から。いきなり8位かよ、というツッコミはなしで。別にありでもいいけど。
こちらには56作品がランクイン。一気に紹介しよう。
~~~~
『青の炎』
『悪童日記』
『家守綺譚』
『ウォーターシップダウンのうさぎたち』
『失はれる物語』
『歌う船』
『海と毒薬』
『音楽』
『籠のなかの天使』
『悲しみの歌』
『狐鷹の天』
『漁港の肉子ちゃん』
『ぎょらん』
『錦繍』
『孤宿の人』
『シーラという子』
『屍鬼』
『十字架』
『ずーっとずっとだいすきだよ』
『砂の器』
『図南の翼』
『零能者ミナト』
『センセイの鞄』
『正欲』
『旅をする木』
『だれも知らない小さな国』
『チグリスとユーフラテス』
『チルドレン』
『月と六ペンス』
『泥流地帯』
『手紙』
『デューク』
『天平の甍』
『毒になる親』
『杜子春』
『とんび』
『ながい坂』
『夏の庭』
『二十四の瞳』
『人魚の眠る家』
『野菊の墓』
『半落ち』
『秘密』
『舟を編む』
『ブレイブ・ストーリー』
『冒険者たち』
『本好きの下剋上』
『美丘』
『模倣犯』
『モモ』
『雪の断章』
『指輪物語」』
『楽園のカンヴァス』
『流浪の月』
『冷静と情熱のあいだ』
『レヴォリューションNO.3』
~~~~
感動といっても色んな感情を内包しているので、こうやって感動作がずらっと並ぶと、そのバラエティっぷりに目眩がしそうである。
日本では「感動=泣ける」みたいな風潮が強く見受けられる。
もちろん泣けるのはそれはそれで良いと思うし、思いっきり泣ける作品に出会うと心が晴れるような感覚を得られて私も大好きである。
ただ泣けることだけを至上とするのはあまりにも勿体ないと思う。身体反応としての涙よりも、もっと複雑で深みのある感情の動かされ方が小説にはあるからだ。
ここで入った作品で具体的なものを挙げるなら、『流浪の月』や『模倣犯』などだろう。とてもじゃないが感動して泣いてすっきりできるような作品ではない。けっこう酷くて救いのない話だと私は思っている。悪口を書いているように受け止める方もいらっしゃるかもしれないが、まあ悪口みたいなものなので全然構わない。悪口が称賛になる作品だってあるのだ。(ちなみに私はどちらの作品も最高だと評価している)
7位
お次は3票獲得の第7位である。
こちらは21作品がランクイン。
~~~~
『100万回生きたねこ』
『アミ小さな宇宙人』
『五分後の世界』
『姑獲鳥の夏』
『キッチン』
『獣の奏者』
『重力ピエロ』
『白夜行』
『大地の子』
『汝、星のごとく』
『八日目の蝉』
『人はなんで生きるか』
『プロジェクト・ヘイル・メアリー』
『容疑者Xの献身』
『生きるぼくら』
『天使の卵』
『流れる星は生きている』
『流星ワゴン』
『世界でいちばん透き通った物語』
『永遠の仔』
『カラマーゾフの兄弟』
~~~~
大好きな作家、森絵都が「長い物語には長くするだけの意味がある」と語っていて妙に印象に残ったことがある。
こうやってネットに雑文を書き散らしてはいるけれど、私は基本的に文章を受け取る側である。与えられることが当たり前になりすぎて、物語が面白いかどうかでしか判断ができていなかった。しかしそこには作者の「どれくらいの長さにするか」という判断が発生していたのだ。
今どきのコンテンツはとにかく短いものがウケていて、長いものはそれだけで敬遠されがちである。音楽だってどんどん短くなっていて、気がつけばそろそろ2分を切るような楽曲だって出てきている。
読書自体がそこまでインスタントに楽しめる趣味ではなくて、本を一冊読もうと思ったら数時間は向き合うことを求められる。
これが映画や音楽だったら絶対に受け入れられない長さである。
実況みたいな刻一刻と変化を見せるようなコンテンツだったら許されるだろうけど、完成品のコンテンツしては異例の長さである。現代人の我慢できなさを思うと、本は衰退するのが必然なのかもしれない。
森絵都が語るのは、つまるところ文脈という意味なのだろうけど、こと感動において文脈は命である。というかそれしか感動を呼ばないと言っても過言じゃないだろう。
金メダルを手にしたとき、命が救われるとき、誰かが手を取り合った瞬間、などなど私たちが感動を覚えるタイミングはたくさんあるけれど、それは文脈を見出すからである。
ただただ"紡がれている"こと自体が感動を呼ぶときもある。これは私たち人間が物語を愛し、連綿と命のリレーを続ける生き物だからだろうか。
このランキングに出てきた作品たちを眺めていると、「最高の文脈がここにあるんだな」「それを突き詰めた世界が閉じ込めてあるんだな」という当たり前だけど、なんだかとても不思議な感覚になる。
6位
あれだな。感動作のタイトルを眺めているだけでなんだか感傷的な気分になってしまって、ポエミーな文章を書いてしまった。
びっくりするぐらい何の作品の紹介もしてなくて、私自身が一番びっくりしている。若い頃に「なんでオッサンって自分語りがこんなに長いんだろ」と冷めた目で見ていたけど、あの視線は確実に今の私に突き刺さっている。でも全然平気。なぜならオッサンだから。嫌われるのが仕事です。どうか笑ってやってください。早く死にたい。
それでは4票を獲得した第6位の発表である。
こちらは11作品のみ。
~~~~
『影法師』
『桜のような僕の恋人』
『博士の愛した数式』
『氷点』
『フランダースの犬』
『ミミズクと夜の王』
『夜と霧』
『レ・ミゼラブル」』
『ストーリー・セラー』
『ライオンのおやつ』
『妖怪アパートの幽雅な日常』
~~~~
いくつか私も読んだことがある作品が入っている。
私はポップな読書家なので古典をほとんど読まない。読書筋力が著しく低いので、普段目にしないような文章や言葉遣いを咀嚼できないのである。
そんな自分にコンプレックスがあり、たまに気合を入れて古典に手を出してみるのだが、先日読んだのが『夜と霧』である。そんなに分厚い本でもないので、これはなんとかできるだろうと挑んだのだが…。
私には無理だった。
完全に心が折れてしまった。文章がとかじゃなくて、人間の邪悪さに耐えられなくなってしまったのだ。
著者は収容所の様子や、収容者たちの心情を非常に冷静に見つめているのだが、こちらは全然それを冷静に受け止められない。普通に感情全開で食らってしまう。あらゆる悲しみや不幸がするすると流れ込んでくる。
「このまま読んでたら自分が壊れる」
大げさじゃなくそう思った。事実という重みと内容の苛烈さが、心に逃げる余裕を与えなかったのだ。なるほど。名作とはこういうことなのか。たぶん違うな。
色んなところで名作だと聞いていたので、最後まで読みきれなかったのは本当に残念である。どれだけキツくとも、つまらなかったとしても基本的には読み切るスタンスでいた。もう私は弱くなってしまったのかもしれない。
5位
さっきから内省的で暗いことばっか書いて申し訳ない。
ここからは素直に明るくなれる作品もちゃんと入ってくるから、きっと私の気分も上向いてくるはずだ。
ということで、5票を獲得した第5位である。
こちらは7作品がランクイン。
~~~~
田中芳樹
『銀河英雄伝説』
うっひょ~~~
最高最高最高!!
説明一切必要無し。
弩級です。面白さが。押し寄せる。感動が。
いや感動よりも面白さの方が押し寄せてくる。面白さで圧死できる。面白死できる。大好きだから殺して。
~~~~
辻村深月
『かがみの孤城』
学校に通えなくなった中学生・こころは、自室の鏡から“孤城”へ招かれる。同じ境遇の7人と〈願いをかなえる鍵〉を一年以内に見つける試練に挑み、共に過ごす中で傷と絆、そして自分自身と向き合っていくファンタジーミステリ。
本屋大賞の中でもぶっちぎりの人気を誇る『かがみの孤城』が遂に登場である。私の紹介の仕方がひどすぎて罵詈雑言を頂戴したのは良い思い出である。
誰もが子どもの頃に抱えていた孤独感に寄り添うような作品で、大人たちがそこら中でボロ泣き報告しててとても微笑ましい。
心に寄り添うような作品という意味では、現代小説の中で最高点を叩き出したのではないだろうか。その役割を一任されているというか。
これからも誰かの心を癒やし、力をくれる存在として読み継がれていくのだろう。
~~~~
夏目漱石
『こころ』
帝大生の「私」は鎌倉で出会った沈黙がちな「先生」と奇妙な友情を結ぶ。東京で続く交流の陰に潜む過去を明かす手紙が届き、愛と罪、近代人の孤独を浮かび上がらせる。明治の終焉を背景に、人間のエゴと救いを静かに問いかけ、師弟の距離が縮まるほど増す不安と、友情と恋の狭間で揺れる心情を重層的に描く心理小説。
今になって思うと不思議で仕方ないのだが、なぜ国語の授業で『こころ』の最初と最後だけ読ませたのだろうか。
名作の入口としては相応しいのだろうけど、ネタバレ許さない人間として生きている私としては絶許(絶対に許さないの意)案件である。機会があったら然るべき場所に討ち入りしたいぐらいだ。
友情と恋と罪悪感を丹念に描き、なんとも言えん感情を与える作品に『こころ』という題を冠したのは素晴らしすぎる仕事である。…と思っていたのだが、夏目漱石作品に詳しい友人に「そんなに考えて付けたタイトルではない」と最近教えられた。おい、私の心が路頭に迷ってるぞ。
~~~~
有川浩
『図書館戦争』
検閲が武力で行われる近未来日本。本の自由を守る図書隊に飛び込んだ新兵・笠原郁は、憧れの“王子様”の記憶を胸に、仲間と共に言論の自由を懸けた実戦と訓練に挑む。恋と成長が交錯する図書館アクション。
これはちょっと意外かも。
問答無用の人気作だとは知ってたけど、感動作としてここまでの評価を得ていたとは。
私は未読なのでそこまで詳しい紹介はできない。しかし皆さんの感想を見ている限りだと、テンポの良さや「コミカル→銃撃→胸キュン」という展開にノックアウトされている印象を受ける。エンタメ性にヤラれているし、表現の自由や検閲といったテーマも入れることで、物語に二重の面白さを持たせている。
有川浩の他の作品を読んだときにも感じたが、彼女は本当に読者の感情を操るのが巧みである。
「手の平の上だなぁ」となんだか悔しい気持ちにもなるのだが、良いもんは良いのだから素直に楽しませてもらおう。
~~~~
青木和雄
『ハッピーバースデー』
実の母親に愛してもらえず、誕生日さえ忘れられてしまった11歳の少女・あすかは、声を失ってしまう。しかし、優しい祖父母の元で自然の営みに触れ、「いのち」の意味を学ぶ。生まれかわったあすかがどんな行動を起こすのか。そして、母親の愛は戻って来るのか…。心に深い想いを刻む、感涙小説。
中学生の課題図書になっていたこちらの作品。
私も中学生のときに読んで衝撃を受けた記憶がある。「ひどすぎるだろ」と幼心に内容の苛烈さへ素直に憤った。
虐待をテーマにした作品なので人によっては過去の嫌な思い出とかがフラッシュバックしてきてしまって読めないかもしれない。
私は親とそこまで険悪になるような関係ではなかったので、冷静に読めた方だとは思うがそれでもキツかった。子供が酷い目に遭う話って、子供が読んでも辛いのよ。
とはいえこちらも長く読み継がれている紛うことなき傑作である。痛みを経験したからこそ届く感動がある。人の成長に痛みは付きものだ。それを改めて教えてくれる作品だと思う。
ブログとはまったく関係ないけど、質問箱でたまに昔読んだ本を探してほしいと私に依頼が来るのだけど、たびたびこの作品が出てくる。
きっと読書好きだけでなく、この作品にたまたま触れた人だったとしても、心に強烈に焼き付いてしまうのだろう。
~~~~
恩田陸
『蜜蜂と遠雷』
無名の天才少年・風間塵、復帰を賭ける元神童・栄伝亜夜、仕事と両立する社会人・高島明石、華やかな王子・マサル。芳ヶ江国際ピアノコンクールで四人は音楽への情熱と葛藤をぶつけ合い、互いの響きに触発されながら“まだ聴いたことのない音”を探す。「ページから音が聴こえる」群像青春譚。
うわー…この感動もあったか!
『蜜蜂と遠雷』はページから音が聴こえることでお馴染みだが、未体験の方がいたら本当にオススメだし、まだこの体験をしていないことが羨ましくて仕方ない。
恩田陸が狂ったように演奏会に通い続けた結果たどり着いた境地である。
演奏の本質に迫りまくって、言葉の限りを尽くし、ときには言葉を削ぎ、空気を作りだし、読者の心も感覚も支配した結果、私たちは「聴く」のである。
さきほど「長い物語には長い理由がある」と書いたけど、こちらに関しては長さによる文脈はもちろんだし、何よりも読んでて心地よすぎるし、ドラマは面白いし、登場人物は最高すぎるしで、とにかくずっと読んでたかった。この長さが嬉しくて仕方ないのである。
~~~~
小野不由美
『十二国記』
平凡な高校生・中嶋陽子は謎の金髪の剣士に導かれ、十二の王と霊獣が治める異世界へ転移する。妖魔渦巻く荒野をさまよい、裏切りと謀略に翻弄されながらも仲間と絆を結び、己を信じる力と“王”としての責務を学んでゆく。多彩な登場人物が織り成す壮大な群像ファンタジー。一方、他の国では若き王や謎の少女らが各々の使命に挑み、交差する運命が世界の均衡を揺らす。
日本が誇るファンタジーといえば『十二国記』。
突出したディテールの細密さで編み込まれた物語で、若年読者を成長小説として夢中にさせる一方、大人には組織論や統治論として楽しめる多重構造も有している。30年以上も愛され続けている実績はダテではない。
とか書きつつまだ私は未読なのであんまり知ったようなことは書けないので許してほしい。
ネタバレを食らわない程度にみんなの感想を検索してみたら「試練ファンタジー」という文言が躍ってて、それだけで厳しい作風が伺えてしまって笑ってしまった。
ちなみに私は完結してないと読み始められないタイプなんだけど、手を出しても大丈夫なのだろうか?誰か教えて。未完に苦しめられるのは『HUNTER×HUNTER』だけで十分ですが。
4位
さあさあ、だいぶ煮詰まってきた。私もテンション上がってきたぞ。
お次は6票獲得の第4位!!
こちらは3作品がランクインである。行ってみよう。
~~~~
宮沢賢治
『銀河鉄道の夜』
孤独な少年ジョバンニは、親友カンパネルラと銀河を走る夜行列車で星々の駅を巡り、乗客との対話を通して〈ほんとうの幸い〉を探す。宇宙の絶景が導く旅の終点で、静かな別れと愛の意味を悟る幻想童話。
さすがの宮沢賢治。
『やまなし』しか知らない私からすると「意味不明な作風」という感じなのだが、絶大な人気っぷりを見るにどうやら私の感性が間に合ってないだけみたいである。本当にすみません。
これまで色んな集計企画をやってきたけど、たびたび上位にランクインしていて、読書家の魂である「名刺代わりの小説10選」では常にベスト3ぐらいに入っていたと記憶している。
それにこのタイトルである。数々のコンテンツでオマージュされている。したくもなるわな。こんな美しいタイトル。
あとこれも最近友人から教えてもらったんだけど、未完稿がいくつもあって、その違いを楽しむ人も多いらしい。凄い世界。
~~~~
梨木香歩
『西の魔女が死んだ』
中学生まいは不登校になり、夏休みを “西の魔女” と呼ばれる英国人の祖母の山の家で過ごす。ハーブ摘みや家事を共にしながら「自分で決め、自分でやり抜く」魔女修業を学び、揺れる心に静かな自信の芽を育てていく成長物語。
魔法使いになれる方法を知れる、稀代の名著である。感動縛りだったら、そりゃこれが入らなかったら嘘でしょう。
不登校に苦しむ孫に対して、魔女のかける温かい言葉の数々がいちいち大人の琴線に触れてしまう。全然無関係なオッサンである私まで「おばあちゃんっ!」と抱きつきたい衝動に襲われる。たびたび本当にすみません。
ゆったりとした物語で温かな空気に包まれつつ、しっかりと沁みる。子供にも大人にもちゃんと支持される作品である。
ということで、いつもの名言を引用しておく。
「サボテンは水の中に生える必要はないし、蓮の花は空中では咲かない。シロクマがハワイより北極で生きる方を選んだからといって、だれがシロクマを責めますか」
~~~~
有川浩
『旅猫リポート』
事故で片曲がり尻尾になった野良猫ナナは、救ってくれた青年サトルとワゴン車で日本各地を巡る旅へ。思い出の友人たちを訪ね歩きながら、人と猫の絆が紡いだ時間と優しさを見つめ直すロードノベル。
口が悪いけど一本筋の通った猫"ナナ"の目線で語られる、飼い主サトルとの日本縦断の物語。
有川浩らしい軽妙な掛け合いで心地よく読ませられ、美しい文章で描かれる日本の風景に心癒される。切なくて爽やかで、こんなん、みんな大好きでしょ。特に猫好きには確実にハマる作りになっていて、「我が愛猫もこう思ってたらいいなぁ」と妄想してしまうこと請け合い。
言葉で描かれているのに、言葉にならない部分で伝わるものがある。これぞ有川浩の真骨頂だろう。読めば心が浄化される。そんな作品である。
ちなみに特に猫好きじゃなかったという方でも、ボロボロに泣いてしまっているそうなので、本当にあらゆる方にオススメである。
3位
それでは7票を獲得した第3位!!
こちらは4作品が同時ランクイン。多すぎてすんません!
素直に集計した結果なので許して。まとめたやつの変な思惑が絡んでない分、純粋に参考になると肯定的に受け取って。
では第3位のひとつめ!!
浅田次郎
『壬生義士伝』
貧しさから家族を守るため、盛岡藩の下級武士・吉村貫一郎は京の新選組へ。剣技と誠実さで仲間に一目置かれつつ、幕末の激動を前に矜持と家族愛の板挟みに揺れる。“南部の鬼”と呼ばれた男の真実を複数の語り手が追い、志・友情・家族愛が交差する歴史群像劇。
「苦しいほど泣いた」
「読み進めるにつれて涙の量が増えていく…」
などなど感涙小説として鉄板の評価を誇る作品。
私は未読なのだけど、評判はあらゆるところで拝見するし、読書仲間からも絶賛の声を幾度も聞いている。あとはいらん情報だと百田尚樹の『永遠の0』関連の話とか。
歴史ものは結構ハードルが高い一方で、一回クリアすると途端にその面白さにハマりがちなので、読まず嫌いになっている人は一度は挑戦してもらいたいと思う。
皆さんの感想を読む限りだと、家族持ちの方は相当食らってボロ泣きしてしまうようなので、吸水性のいい布の準備をしておいたほうが良さそうである。私も誰もいないところで読もう。
~~~~
お次は第3位のふたつめ!!
これだっ!!
三浦綾子
『塩狩峠』
誠の心、勇気、努力。
大勢の乗客の命を救うため、雪の塩狩峠で自らの命を犠牲にした若き鉄道員の愛と信仰に貫かれた生涯を描き、人間存在の意味を問う。
結納のため、札幌に向った鉄道職員永野信夫の乗った列車は、塩狩峠の頂上にさしかかった時、突然客車が離れて暴走し始めた。声もなく恐怖に怯える乗客。信夫は飛びつくようにハンドブレーキに手をかけた……。明治末年、北海道旭川の塩狩峠で、自らを犠牲にして大勢の乗客の命を救った一青年の、愛と信仰に貫かれた生涯を描き、生きることの意味を問う長編小説。
ド直球の名作続きでなんだか申し訳ない気分になっている。感動を主軸に据えてランキングにすると、こんな贅沢なことになってしまうんですね。ありがたや。
さて『塩狩峠』である。
この作品を"感動"と簡単に一言で表していいのか非常に悩むところなのだが、これだけの票が集中しているのだから、きっと感動と評するのが一番相応しいのだろう。
実際の鉄道事故を題材に、信仰や差別、命や生き方について、深く深く考えさせられてしまう剛力な作品である。
深く感動させられる作品というのは、読んだあとの世界の見え方を変える力がある。また、これまでの自分の生き方やこれからの人生について、考えざるを得ない強制力がある。
『塩狩峠』は青年の信仰に対する葛藤を描いているが、これはなにもキリスト教だけに限らないし、信仰があるかどうかに収まる話でもない。誰もに通ずるテーマを内包している。つまりは「私たちの心は、命は、何のためにあるのか?」ということである。
短い話だが、色んなものを授けてくれる名作である。
そしてそれはきっと、読み手の今後の人生において宝物になるはずだ。
~~~~
さあどんどん行こう。第3位のみっつめは、こちら。
百田尚樹
『永遠の0』
司法浪人生の佐伯健太郎とフリーライターの姉・慶子は、祖母の遺言を手がかりに、太平洋戦争で「零戦の天才」と呼ばれた宮部久蔵の足跡を追う。命を何より尊びながら特攻へ向かった謎を解くため元戦友を訪ね歩き、家族愛と信念が時代に翻弄された真実に迫る、命と戦争を問うヒューマンドラマ。
作者の顔が前に出すぎて、読書体験を損ないそうな感じだが、私はまだ百田尚樹がうるさくなる前に読んだので純粋に感動させていただいた。
これから読む方々や、百田尚樹があんな感じになってから読んだ皆様はどうだったのだろうか。一応念の為に言っておくか。ご愁傷さまです。
『永遠の0』はとにかく泣ける。私もどろんどろんに泣いた。疑いようのないほど私はいいオッサンなので、問答無用に涙もろい。だがそれにしたって『永遠の0』はボロ泣きだった。
これまでに泣ける小説は大量に読んできたけど、単純排出体液量で換算するなら『永遠の0』が一番だろう。長いうえに泣けるポイントが多すぎるのだ。確実に読んで体重減ったと思う。次点は重松清の『とんび』である。こちらもどうしようもないほどの感涙小説なのでオススメ。
戦時をテーマにした話なので、尊い命に思いを馳せたりとか、特攻についてとか、色々考えさせられる部分はあると思うが、なんかそこまで深入りする必要を感じないから不思議な作品である。
~~~~
それでは、第3位のラストを飾るのはこちらの作品。
遠藤周作
『沈黙』
17世紀江戸初期、潜伏キリシタンを訪ね来日した司祭ロドリゴは、信仰と棄教の葛藤に沈黙する神と向き合う。踏み絵や拷問に揺れる己の信念を通じ、人間の弱さと赦しを問う静謐な長編小説の傑作。
これまた強烈に重いのが登場。
内容が内容なので私のような軽薄ものが軽々しく紹介していいものか悩んでしまいそうになるが、まあ後で告解すればいいでしょう。
実は私は原作を未読でスコセッシ監督の『Silence』を観てしまったので、そちらの印象で話を進めるのを許していただきたい。あ、"赦して"か。
凄い作品だとは知っていたけど、"沈黙"という言葉がいくつもの意味を孕みながら、読み手の価値観を昇華していくストーリーはまさに圧巻であった。
信仰心の欠片も持ち合わせない私のような愚か者にも確実に福音というものの真の姿を垣間見せてくれたと思う。遠藤周作、とんでもねえ。
私は極度のタイトルフェチで、タイトルだけで美味しいやつ(昨日星を探した言い訳、とか私の頭が正常であったなら、とか)も大好物だけど、シンプルなのに作品を読み進めるうちにタイトルの意味が比喩で回収されるのが本当に堪らない。
『沈黙』はそういう意味では最高峰の回収っぷりだった。
最初は単純に「神の沈黙」についてだけだと思っていたら、そこからまあ深く切り込むこと。あれはザックリやられるわ。
もちろんタイトルだけに限らず、人間の残酷さや醜さも見せつけられるし、他にも色んな要素が絡んでくる。そのどれもが骨太で、大ダメージを食らわせてくるので読み終えるころには満身創痍になるはずだ。
でもその痛みこそ物語を味わう醍醐味だと私は思うし、みんなにとっても同じであってほしいと信じている。
2位
佳境も佳境、8票を獲得した第2位!!
ひとつめは、こちら!!
森絵都!!
『カラフル』!!
死んだはずの魂が抽選で“人生再挑戦”の権利を獲得。天使見習いプラプラに導かれ少年・小林真の体に入り、期限内に自らの“大きな過ち”を思い出し人生を塗り替えるチャンスに挑む、色彩豊かな再生物語。
私がこの名作に出会ったのはたしか二十歳のとき。
森絵都のことはその前から好きだった、というかそもそも私が読書好きになったのは森絵都のせいである。読書という世界に引き込んでくれた恩人であると同時に、読書に取り憑かれた人生に捻じ曲げた主犯である。その節はどうも。
で、いっぱしの大人になってから読んだっていうのに、もう食らう食らう。これで完全に森絵都の筆に忠誠を誓ったね。「これが読書か!」って開眼させられた感じ。小説のハードルが上がったと思う、『カラフル』のせいで。
色んなものを与えてくれる作品だけど、やっぱり私的に一番はタイトルの秀逸さである。
『カラフル』というタイトルを見たとき、最初は「あー、なるほど。なんか世界はとっても豊かな色彩を持ってる的な話なんでしょ」と完全に舐めていた。
ところがどうだ。作品を読み進めるにつれてこのタイトルの持つ意味や、世界を見通すひとつの比喩としてなんと秀逸なのかが分かる。
私がタイトルフェチになったのも『カラフル』のせいである。どんだけ人の人生を歪めれば気が済むんですか。
~~~~
第2位のふたつめは、こちらっ!!
ミヒャエル・エンデ
『はてしない物語』
いじめられがちな少年バスチアンは、不思議な赤い本『はてしない物語』を手に入れ、読み進めるうちに物語世界ファンタージエンと現実が交差し始める。本の中の若き戦士アトレーユが闇に立ち向かう姿に惹かれたバスチアンは、自身も想像力と勇気の試練へ誘われる。主人公=読者という体験が展開する壮大なファンタジー。
唯一無二の読書体験ができる、マジもんの世界的ベストセラー。傑作ファンタジーの代名詞。
読者を物語に連れて行く、という意味ではこの作品を超えるものはないんじゃないでしょうか。大体にしてそれが目的の作品だし。こんな作品と未成年のうちに出会ったら、絶対に本好きになってしまうよなぁ。今だったらその役割が『ハリー・ポッター』なのかもしれないけど、やっぱり「本を愛する」という意味では『はてしない物語』が最強。これ一択でしょう。
未読の方にはぜひともハードカバーで読んでいただきたいと思う。装丁も込みでこの作品が成り立っているから。もちろん物語だけでも最高なのは間違いないんだけどね。
それにしてもミヒャエル・エンデは『はてしない物語』といい、『モモ』といい、人間の根源に強く訴えかけつつ、平易な物語に落とし込めるのが凄すぎる。
ということでついでにモモも宣伝。
1位
それではラストである。
「一番感動した本ランキング」の栄えある頂点に輝いたのは…
ダニエル・キイス!!
『アルジャーノンに花束を』!!
知的障がいを持つ青年チャーリイは、脳手術で知能向上を図る実験に志願する。成功例とされる白ネズミ・アルジャーノンに励まされながら、急速に広がる学びと感情のギャップ、周囲との関係変化に戸惑い、己のアイデンティティを模索する姿を日記に綴る。知識が増すほど芽生える孤独や恋心も繊細に描かれ、〈人間らしさ〉を問いかける。SF要素と心理描写が絡み合う、永く愛される名著。
おめでとうございますっ!!
まあ妥当of妥当でしょう。
テーマ、構成、表現力、表現手法とどこを取っても完全無欠の作品で、人生のどこのタイミングで出会っても名作と思える稀有な作品である。
私たちの感性は悲しいかな、年齢を重ねるごとに摩耗していって、新鮮な感動を味わえるのはどうしても人生の初期段階になりがちである。その分、年齢を重ねてから味わう感動には深みがあるのだけど。
『アルジャーノン』の場合、扱っているテーマがあまりにも幅広いので、その全部を味わってもいいし、一部が深く刺さってもいいし、全部が深く刺さって致命傷を負ってもいいという、とっても全方位に無敵な作品である。
私はといえば出会った中学時、生粋のバカだったので、本の仕掛けに興奮して中身はどうでもよかったクチである。どうか罵ってほしい。あのときの私は間違いなく何も知らなかったし、幸せだった。たぶん今もそうかも。
ちなみに以前の企画で「大好きな鬱小説」でも上位にランクインしていたので、人によっては大ダメージを食らうことになるので、その点だけ注意。でも基本的には人生を大きく肯定してくれる作品だと思うし、希望の物語だと私は信じている。
ということで、一番感動した本ランキングの頂点に輝いたのは、世界で一番有名な白ネズミでした。おめでとうございます!!
以上。最後までお付き合いいただき感謝。
ぜひTwitter(人呼んでX)でコメントとか、記事を拡散していただけると助かります。
※集計作業を頑張ったひろたつを労ってあげたい方はこちら。