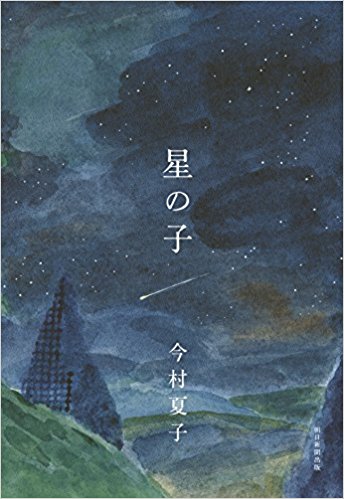
どうも、読書中毒ブロガーのひろたつです。
今回の記事は「2018年本屋大賞ノミネート作品全部読み終わるまで永遠に筋トレする」という企画の第9弾である。やっとここまで来た…。
一応参考までに、ノミネート作品を以下に羅列しておく。
この中から今回紹介するのが…
『星の子』!!
主人公・林ちひろは中学3年生。
出生直後から病弱だったちひろを救いたい一心で、
両親は「あやしい宗教」にのめり込んでいき、
その信仰は少しずつ家族を崩壊させていく。
純文学が苦手な人でも問題なし
2018年本屋大賞ノミネート作品の中で、唯一純文学っぽい作品である。
私は小説好きではあるが、正直なところ純文学を得意としない。一時期頑張って芥川賞作品を読み漁ったことがあるが、結局楽しみきれないまま終わってしまった。どうやら実力不足だったようである。
しかし、こちらの『星の子』、めちゃめちゃ面白く読んでしまった。
もしかしたら純文学じゃないのかもしれないし、ただ単に運良く私のツボに入っただけかもしれない。とにかくかなり面白い。
読む前にAmazonのレビューをボンヤリ眺めた感じだと、かなり評価が分かれていて、「なんでこんな作品が本屋大賞にノミネートした?」と不思議に思っていたが、読んでみて納得、なるほどこれは確かに認められるだけのことはある。
ただ、みんなの評価が分かれるのも頷けたりする。
今回はその辺りにも触れながら、この問題作について解説していきたいと思う。
普段であれば本の紹介記事では「ネタバレは一切なし!」と豪語する私なのだが、こちらの『星の子』に関して言えば、ネタバレしても作品の面白さに影響がないと思うので、内容に触れることにする。
少しでも内容を知りたくない方は、容赦なくブラウザバックしていただきたい。
では行ってみよう。
スポンサーリンク
最大の魅力は、洗練された文章
まずは『星の子』の魅力について語ろう。
さすがは芥川賞の候補に挙がった実績を持つ作者である。非常に文章が巧みである。
というか、この今村夏子の文章の場合「上手い!」と読みながら認識するタイプの上手さではなく、読み終わってから「そういえば夢中になってたな」と後から気付くタイプの上手さである。これって、実はけっこう貴重な能力である。
そもそも小説というのは、文章だけを使って、読者の脳内に物語を注入する媒体である。読者が夢中になればなるほど、目的を果たすと言えるだろう。
となると、どんなに面白い小説であっても、読みながら読者が「面白い!」とか「凄え!」なんていうふうに俯瞰した感想を抱いてしまうのは、物語自体からすればノイズである。
スポーツの応援みたいなものかもしれない。観客の俯瞰した応援は盛り上がるためのファクターになるかもしれないが、試合の本質には影響しないし、むしろ悪影響を及ぼす可能性がある。
つまり今村夏子の「気付かれないように読者に物語を注入する能力」というのは、小説家にとって実は、一番純粋で大事なものなのかもしれない。
ネタバレの影響を意に介さない物語
もうひとつ『星の子』の大きな魅力がある。
それが「ネタバレの影響を受けない」ということである。
世にあるほとんどの物語は、ネタバレによって元々あった魅力が消失する。あらすじだって2,3割は面白さを失わせている。
これは多くの人が求める「先の読めない展開」とか「意外な結末」に依存する物語がほとんどだからである。
そういった物語は快感度が高い。人は快感の奴隷であり、快感を提供してくれるものには惜しみなく対価を支払う。だからこういった作品がずっと人気を維持している。別に悪いとか言ってるのではなく、単にそういう傾向がある、というだけの話。実際私もそういった物語が大好きだ。
しかし、情報の奔流にのまれたような生活を送っている我々にとって、「ネタバレ」は切っても切れないものである。そこら中にネタバレが揺蕩っており、誰しもが大なり小なりネタバレの脅威に晒されている。
ネタバレを完全に避けようとするならば、まずネットは完全にシャットアウトだし、本の帯や本屋のポップもネタバレをしてくるので、目を瞑ったまま適当な本を買って、いきなり中身を読み始める、という方法しかない。
それぐらいネタバレを避けるのは難しい。
だからこそ『星の子』のようなネタバレに影響を受けない作品の価値が高まる。
たしかに巷でウケるような「先の読めない展開」とか「意外な結末」はないかもしれない。エンタメ性は低めだ。
だけど、この作品は確実に読者に「物語を体験させる」。
小説の本来の役割を、着実にこなす仕事人なのである。
見事な評価の分かれっぷり
この記事を書いている2018年4月現在、Amazonでの『星の子』の評価は以下のようになっている。
☆5…29%
☆4…28%
☆3…14%
☆2…11%
☆1…18%
びっくりするぐらい、万遍なく評価が分かれている。
私個人の意見を書かせてもらえるならば、作品を評価するときに☆5や☆1を付けてしまう人は、ちょっと感情的すぎる気がして好きではない。小説作品のAmazon評価を見ていると、大抵☆5か☆1に偏る傾向があるので、『星の子』のこのパターンは非常に珍しい。
さて、ではなぜこのように『星の子』の評価が分かれてしまうのか。
以下にその理由を書いていく。
物語らない物語
『星の子』には大衆受けする作品とは、一線を画する仕掛けが施されている。もちろんこれは「意外な真相」的なことではなく、売れる作品であれば絶対にやらないことをやっている、という意味である。
最初にも書いたが『星の子』は、今村夏子の巧みな筆によって、読者は軽やかに物語を脳内に展開することができる。
しかしながらその一方で、『星の子』は「物語を放棄する」というスタンスを取っている。
ここが『星の子』の評価が分かれる大きな要因になっている。
矛盾しているように思えるだろうか。巧みに物語りながらも、実は物語を放棄しているのだ。
物語って何?
少し説明しよう。
物語とは、簡単に言うならば「問題が起こり、解決すること」である。これは非常にざっくりとした言い方だが、「大衆が求める物語のひな形」という意味で真である。
多くの人はそこに物語があるだけで、何か問題が起こり、そして解決されるものだと決めつけている節がある。
しかし本来物語はもっと自由なはずだ。そこでどんな物語が展開されようとも、作者の表現の自由であり、それは受け手が決めることではない。受け手が決めるのは、ただひとつ、「その物語をどう受け取ったか?」だけなのだ。
ここが物語の難しい所である。
これが食べ物であれば、例えば自分が「蕎麦が食べたい」と思えば蕎麦屋に行けばいい。上手い不味いの差はあれど、そこでは確実に蕎麦が出る。
しかし物語はそうではない。
「こんな感じの物語で、きっと面白いに違いない(快感をもたらしてくれる)」と期待したとしても、オーダー通りのものが出てくる可能性は低く、さらに言うとそこに「上手い不味い」も加わってくる。しかも最後まで見ないとそれが分からない。とんでもなくリスキーだ。でもそれが物語というものの性質なのである。
委ねられるもの
このように考えていくと、ひとつの真実が見えてくる。
物語というのは作者によって生み出されるが、実はその実体は読者の中にしか存在せず、物語を形にするのはあくまでも読者自身の力に委ねられているのだ。
どれだけ懇切丁寧な説明をしても勘違いする人がいるように、人の理解というのは本当に千差万別だ。同じ物語を目にしても、各々の中で展開される物語はきっとまったく違うものに仕上がっていることだろう。
つまりこれを極論すると、「物語を面白いと思うかどうかは、読者の責任」なのである。作者はあくまでも材料を出しただけ。あとはお好きなように、という具合である。
さて、『星の子』に話を戻そう。
この作品には色んなテーマが絡み合っている。「宗教」「信心」「貧困」「青春」「恋愛」「友情」「自我」「自立」などなど、こうやって並べてみると非常に豊穣な物語に思える。
しかし『星の子』では、いや今村夏子は、と書く方が正確かもしれない。彼女はそれらの要素に対してふわっと触れていくだけで、それぞれの要素でもろにドラマが展開されることは一切ない。
問題は起こすが、解決はしない。作中で起こる出来事に対して、どのような形を与えるか、完全に読者に委ねているのだ。
この姿勢を作品中、一貫している。
そしてその姿勢は物語の最重要部分とも言える「結末」においても同様である。結末もまた、今村夏子は私たちに“委ねて”しまっているのだ。
読者責任型小説
このように、元々物語とは読者の責任が非常に大きいものなのだが、『星の子』はその責任の所在がより顕著な作品なのである。
なので「物語とは作者が読者を楽しませるもの」と決めつけてかかり、自分の責任をまったく認識できない人にとっては、「作者が無責任!」と批難の対象になりえる。彼らにとっては非常に評価のしにくい作品になってしまうのだ。繰り返すようだが、それが悪いと言いたいのではない。そう感じる人がいる、というだけの話である。
またその一方で、この特有の“投げやり感”を新鮮に感じる人もいることだろう。
売れ線の本ではなかなか味わえない妙味である。料理でもそうだが、複雑さはときに思わぬ深みを生み出すことがある。もちろんそれをどう判断するかは人それぞれである。
終わりに
色々書いてきたが、私の素直な感想は最初に書いた通り「面白い」である。バカみたいな感想だが、本音である。本音なんて基本的にバカみたいなもんだ。
これだけあそび(余白の意)がある作品なので、読者のそれぞれで好きなだけ展開させることができる。この記事のように、だ。これこそが読書の醍醐味ではないだろうか。
たしかに分かりやすい「エロ」とか「グロ」とか「暴力」とか「意外な結末」みたいなエンタメ要素はないかもしれない。
だが『星の子』には、私たちが求める“理想の物語”がある。
それは断片かもしれないし、鏡のように「物足りない…」と思わせることで感じさせるかもしれない。
だが、何度でも言おう。
そこにはあるのだ。あとは見つけるだけである。
以上。
読書中毒ブロガーひろたつが、生涯をかけて集めた超面白い小説たちはこちら。




