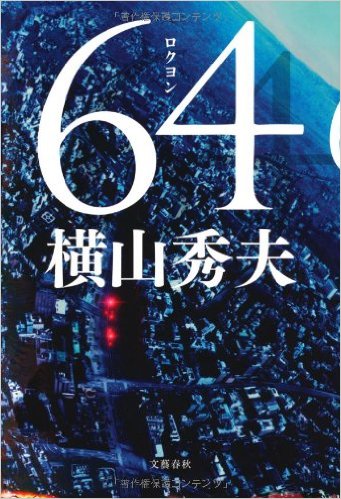
どうも。
ファンが待ちに待った作品
はず始めに言っておきたいことがある。
今回紹介する『64(ロクヨン)』は間違いなく横山秀夫のキャリアの中で最高傑作と呼ぶに相応しい作品だということだ。
『64』が発売されたのは2012年。前作の『震度0』が発売されたのが2005年だったので、私たち横山ファンはなんと7年もの間、沈黙を耐え続けていたわけだ。その間、セオリー通りとも言うべきか、横山秀夫死亡説が流れ、体調不良説が流れし、いつの間にかファンの間では「もう新作は望めないかも…」という絶望とも諦めともつかない思いに捕らわれていた。それも仕方のないと言えるほどの時間だった。
そしてそれだけの時間を待ったからこそ、『64』は嬉しかった。待ちわびた作品だった。期待も高まるけども、それよりも待ち時間が長すぎて「これだけ待ったのだから、64を駄作だと評価したくない」というバイアスがかかっていたことも認めよう。
だがそれでも言おう。何度でも言おう。『64』は傑作である。横山秀夫作品の中で最高傑作であると。
スポンサーリンク
内容紹介
毎度のことながら、私は「あらすじさえもネタバレである」という持論を掲げている。もし私の本の選球眼を信じていただける方、または上記の文章から何か尋常ならざる熱意を感じられる感度の高い方は、ぜひともこのままこの記事を読むのは止めて、『64』を無条件に読んでもらいたいと思う。
| 64(ロクヨン) 上 (文春文庫) | ||||
|
ここから先はあらすじを若干込みで(だけれども内容にはほとんど触れずに)内容紹介と『64』の魅力を伝えていきたいと思う。
まずアマゾンの紹介文を転載しておく。
警察職員二十六万人、それぞれに持ち場があります。刑事など一握り。大半は光の当たらない縁の下の仕事です。神の手は持っていない。それでも誇りは持っている。一人ひとりが日々矜持をもって職務を果たさねば、こんなにも巨大な組織が回っていくはずがない。D県警は最大の危機に瀕する。警察小説の真髄が、人生の本質が、ここにある。
警察小説の真髄がここにあるかどうかは私には正直分からない。真髄という言葉はそんなに簡単に使う言葉ではないとも思う。
だがしかし、ここで分かって欲しいのは、「ここに警察小説の真髄がある!」と評価した人が実際にいるという事実である。
よく「絶対なんてないよ」という言葉を見かけるが、それはそれで真である。だがそうは言っても世の中には「絶対」という言葉を使う人は大多数いて、その人たちの「絶対」というのは、「100%確実」という意味よりも、「絶対と言いたいぐらい信じてほしい」というのが精確だと思う。
言葉の意味自体よりも、なぜそんな言葉を使いたくなったのかの方が重要になることもあるということだ。
興奮しちゃうよ
今、この記事を読んでいる方の中に「話が逸れているんじゃないか」と思われている人も多いだろう。その通りだ。はっきり言って、私は完全に脱線していた。
というか、この傑作小説『64』を冷静に紹介しようというのがそもそも無謀なのだ。これだけの作品に触れて、しかもそれを不特定多数の人々に勧めるための文章を書くとなったら、そりゃあもう頭のネジも外れかけるというものである。少々の不手際は勘弁してもらいたいし、なんならもう紹介文になっていなかったとしても「ああ…取り乱してしまうぐらいの傑作なんだな。よし読んでやるか」ぐらいに受け取ってもらいたい。
それぞれに言いたいこと
またしても本筋とはまったく関係ない話をしてしまって申し訳ない。
さて、『64』をこれから読もうと思っている方に向けてこの記事を書いている訳だが、皆さんは2パターンに分けられる。
ひとつは、すでに横山秀夫作品に触れており、作者の特徴や味を知っている方。
もうひとつは、映画などで興味を持たれ、まだ横山秀夫作品の味わいを知らない方。
まずすでに横山秀夫作品を読んでいる方に言いたい。もう読めと。すぐに読めと。何を悩んでいるのか。上下巻に分かれたあの分量だろうか。甘い、甘すぎる。『動機』や『第三の時効』の興奮を覚えているだろうか。あの興奮が、ドラマが、熱さが、上下巻の間、ずっと繰り広げられるのだ。これほど濃密な読書体験があるだろうか?こんな贅沢な時間がどこにあるだろうか?悩むだけムダだ。答えはひとつだ。
次に横山作品を未読の方に言いたい。
まず私は小説の映像化作品を観ないようにしている。その理由を書き出すと、1万字はゆうに超える駄文が完成してしまう。それは後々の機会にしておこうじゃないか。
なので映画版『64』との比較をすることは私にはできない。だがひとつだけ確実に言えることがある。それは「映画よりも遥かに面白い」ということである。もし映画版『64』を観てしまっているのであれば、ストーリーを大体把握してしまっているので、それは不幸だと言わずにはいられないが、小説には映画を圧倒的に超えるボリュームがあること、そして映像よりもはるかに登場人物たちの内面に肉薄した内容になっていることで補えるのではないだろうか。
もし映画版『64』を未見なのであれば何ら問題ない。むしろ「初横山」というのは羨ましい状況でもある。存分に小説的快楽に溺れてほしい。極上でっせ。
スポンサーリンク
ちゃんと魅力を伝えよう
ここまで結局何一つ魅力を伝えられていないので、ちゃんと膝を正して作品に向き合いたいと思う。
まず横山作品のどれもに言えることだが、登場人物たちの内面描写と、それを存分に駆使した駆け引きや葛藤が堪らない。これはなかなか若い作家には出せる技ではないだろうし、若い登場人物でも味わえないものだろう。年齢を重ね、色んなしがらみがある中年以降だからこそ現れる深みである。
登場人物たちの苦悩というのは物語にとってスパイスだ。それも極上の。いくら綺麗事を言おうとも、人は「他人の不幸は蜜の味」であり、物語の登場人物たちに降りかかるトラブルは「楽しみ」でしかない。存分に楽しんでもらいたい。
謎を脳みその中に作り出す
かなりマニアックな話をしたい。興味がない人は読み飛ばしてもらって構わない。
『64』は推理小説というジャンルに属する作品である。警察小説でもあるのだが、その辺りはまあ置いておくとしよう。
推理小説というのは、平たく言うと「作品内で謎を提示し、読者を翻弄しつつ、意外な結末で、しかも論理的に謎を明らかにする小説」である。私の頭が悪いので説明文はめっぽう苦手なので勘弁してもらいたいのだが、まあそういうことである。
デビュー当時は切れ味抜群の推理小説ばかりを横山秀夫は発表していた。名作ばかりだった。
例えばさきほど挙げたこの2作品は鉄板中の鉄板である。
| 動機 (文春文庫) | ||||
|
| 第三の時効 (集英社文庫) | ||||
|
しかし後期になればなるほど、謎の切れ味は鈍りはじめ、遂には推理小説自体を書かなくなるときもあったぐらいだった。それはそれで彼の味ではあるのだが、若干物足りなかったのも事実。ちなみに『クライマーズ・ハイ』は大好きである。
| クライマーズ・ハイ (文春文庫) | ||||
|
で、推理小説のおきまりパターンと言えば、密室を代表とされる「どうやって犯人は犯行を行なったか?」というものである。これはこれで素晴らしい世界だし、私も大好きである。
だが、横山秀夫の提示する謎は一味違う。謎を登場人物たちの頭の中に作り出すのだ。
これはちょっと分かりにくいかもしれない。
例え話をしてみよう。
あなたが学校に行くと、校門の前に大量に机と椅子が積み上げられていた。夜中に各教室から運び出されたものらしい。
これだけを見ると学校に行きたくない人間の犯行かのように思えるが、実はこの事件の1週間後には林間学校があり、それはこの学校の生徒、教師がみんな楽しみにしているイベントでもある。またさらに1週間待てば夏休みに入る。ここで余計な事件が起こってしまうと夏休みに登校するというハメになってしまう。誰も得をしない状況だ。
しかし、犯行を行なったのは生徒以外有り得ないという。実は目撃者がいたのだ。夜中に教室の窓を出入りしている生徒の姿を見た人が。
その窓はどうやっても子供しか通り抜けできないサイズであり、近隣の大人や卒業生が犯行に及んだとは考えられないのだ。
これによって、犯人は大体目星はつくが、どう考えてもその犯人の利益になりそうにない状況。それは犯人の境遇や狙いなど、色んな角度から検証すればするほど謎が深まるというもので、これが頭の中に作り出される謎になる。
上でも書いたが横山秀夫の心理描写は極上である。登場人物たちの葛藤は人間そのものだ。だからこそ、彼の頭の中に浮かび上がる謎は余計に味わいを増す。不可能性、謎性が格別なのだ。そこが本作の肝とも言えるだろう。
物的証拠や状況証拠に左右されない、純粋なる人間ドラマの向こう側に謎の真相が待っているという状況は、ページを捲る手をグイグイ動かしてくる。というかもうページを捲っていることなんてすぐに忘れてしまうだろう。いつだか又吉が読書芸人で「本の中に入る」と言っていたが、まさにそれである。ページの中に迷い込んでほしい。
警察だが警察にあらず
我々市井の人間からすれば、警察という組織に所属している人間なんてみんな同じに見えるが、内情はどうやらまったく違うらしい。
横山秀夫はもともと新聞記者をやっていたこともあり、その辺の内情には異常に詳しい。専門用語もポンポン出てくる。汚職事件のことを「さんずい」とかね。
『64』 の中で大きく取り扱われるテーマとして、「刑事部VS警務部」というものがある。実働部隊と補佐と考えればよく分かると思う。
主人公の三上は元刑事の現警務。広報官という、メディアに対する仕事を専門とする、主人公としては若干珍しい立ち位置を用意している。
しかしこれが物語に最高の効果は発揮している。
モロに刑事だったら、もっとまっすぐな物語になっていたと思う。言い方は悪いが、どこにでもある警察小説だったと思う。つまらなくは勿論ないが、「唯一無二ではない」という程度の作品だった。
だが、これは「元刑事。だけど今は直接手を出せない警務部」という立ち位置にしたことで、主人公にしがらみや葛藤を増やし、物語に深みを出しているのだ。結末に一直線なんてことは普通の人生ではありえない。上手くいかないのが普通なのだ。
だからこそ『64』の結末で、ある部分に関しては未解決のままで終わらせてしまうのだが、それは読んでからのお楽しみとしておこう。私見ではあるが、あれは作者なりのフィクションと現実とのバランスの取り方だったように感じている。
ぶつかりながら、もがきながら、ときに立ち止まる主人公の姿を見ながら、一緒に苦しむといいだろう。きっとあなたは三上と同化するはずだ。そこに人間の姿を見るはずだ。
果たして伝わるだろうか
勢いに任せて5000文字以上も書き連ねてしまったが、果たして傑作小説『64』の魅力を伝えられていたのかはまったく分からない。最初に書いた通りになってしまった。
これもひとえに私を興奮の筆に走らせてしまった『64』が悪いのであって、こんなに面白い作品を世に生み出してしまった横山秀夫が悪いと断言する。私の他の紹介記事を読んでもらえば分かると思うが、もっと丁寧に魅力を伝えられている。
決して他の作品が劣っているという訳ではないのだが、やはり興奮にどうしても筆が滑らずにはいられないという部分が大きく、また魅力が一筋縄では語れない部分が多数あることも影響しているだろう。まあ結局は処理しきれない私がバカなだけとも言えるが。
こんな駄文の羅列を誰が読んでくれるのかはさっぱり分からない。だがこれが正真正銘、『64』にやられた人間の紹介文だと理解してもらえたら幸いである。
以上。
| 64(ロクヨン) 上 (文春文庫) | ||||
|







