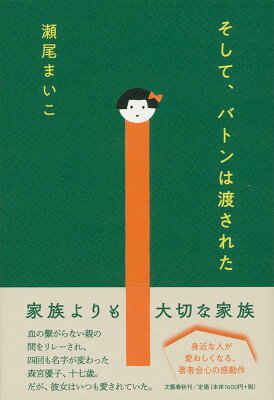どうも、読書中毒ブロガーのひろたつです。
皆さまいかがお過ごしでしょうか。
私は今日も忙しい日々を過ごしていて、職場ではにこやかな上司を演じながらも、その実、胸の内では常に誰かしらに殺意を抱きながら暮らしております。人間関係って、つまりは「周りにいる人間の誰に殺意を抱くか」ってことでしょ?
仕事柄、人と接する機会が多く(部下が100人超)、常にウンザリしながら毎日を乗り切っている。
そんな心身ともに疲れ切った私を潤してくれるのが読書である。
正直、私は本のおかげで生きていけている。本がなかったら、颯爽とこの世から姿を消していることだろう。
で、今回の記事である。
読書家であれば心躍らずにはいられないイベント、「本屋大賞」についてだ。
書店員が今一番売りたい本を決めるこのイベントでは、他の賞レースにはなかなかない大衆性があり、初心者からマニアまで楽しめるとっても間口が広いことが特徴だ。私も何度お世話になったか分からないぐらいだ。下ネタではない。
そして先日、2019年の本屋大賞ノミネートした10作品が発表された。
こうなったら読書中毒ブロガーがやることはひとつだけでしょう。
勝手に予想、である。
顔も見えない素人の予想なんて誰が読むんだ、という話なのだがこれはもうマニアの習性、業のようなものであり、やらずにはいられないのである。ノミネート作品についてグダグダ言わずにはいられない。もはや呪いだ。
ということで、これから私の偏見と思い込みと先入観とバイアスに満ちた予想を発表していきたいと思う。
参考にするもよし、感心するもよし、「なに勝手なこと書いてやがんだこの野郎、殺すぞ」と批判するもよし。好きに楽しんでもらえたら、こんなにマニア冥利に尽きることはない、というのはさすがに言いすぎだが、私が必死に文章を綴った時間が無駄にならずに済む。
では行ってみよう。
スポンサーリンク
※ちなみにまだどの作品も未読です。
ノミネート作品の紹介
まずは今回のランキングで勝負する選手たち(ノミネート作品)を紹介しよう。
ベルリンは晴れているか
1945年7月。ナチス・ドイツが戦争に敗れ米ソ英仏の4ヵ国統治下におかれたベルリン。ソ連と西側諸国が対立しつつある状況下で、ドイツ人少女アウグステの恩人にあたる男が、ソ連領域で米国製の歯磨き粉に含まれた毒により不審な死を遂げる。米国の兵員食堂で働くアウグステは疑いの目を向けられつつ、彼の甥に訃報を伝えるべく旅立つ。しかしなぜか陽気な泥棒を道連れにする羽目になり――ふたりはそれぞれの思惑を胸に、荒廃した街を歩きはじめる。
作者の深緑野分(ふかみどり のわき、と読む。すげえ名前)は、2016年の本屋大賞ノミネート作品『戦場のコックたち』に続き、二度目のノミネート。寡作な割には凄い打率である。
作家としての知名度は低めだが、大賞を獲得して人気作家の仲間入りなるか。(←現時点で人気がないとは言っていない)
フーガはユーガ
常盤優我は仙台市内のファミレスで一人の男に語り出す。双子の弟・風我のこと、決して幸せでなかった子供時代のこと。そして、彼ら兄弟だけの特別な「アレ」のこと――著者一年ぶりの新作書き下ろし長編は、ちょっと不思議で、なんだか切ない。
面白い本しか書けないという奇病に罹っている作家、伊坂幸太郎。今作も当然のノミネート。
伊坂幸太郎は、過去に大賞を獲得していることもあり、読者のハードルも異常に上がっていて、かなり厳しい状況。恩田陸に続き複数回受賞なるか。(←毎度クオリティが文句なしだから、言いたいことがほとんどない)
火のないところに煙は
「神楽坂を舞台に怪談を書きませんか」。突然の依頼に、かつての凄惨な体験が作家の脳裏に浮かぶ。解けない謎、救えなかった友人、そこから逃げ出した自分。作家は、事件を小説にすることで解決を目論むが――。驚愕の展開とどんでん返しの波状攻撃、そして導かれる最恐の真実。読み始めたら引き返せない、戦慄の暗黒ミステリ!
紛争地域ぐらい地雷臭が半端じゃない作品。
普段であればとてもじゃないが怖くて手を出せない類の作品だが、本屋大賞を信じて真っ先に買ってしまった。この記事を書き終わったら一番最初に読む予定。
「驚愕の展開」「どんでん返しの連続」という煽りワードに負けないだけの質を担保できていれば、大賞受賞は間違いなし。期待しよう。(←いつもそれで騙されてんじゃねーか)
ひとつむぎの手
大学病院で過酷な勤務に耐えている平良祐介は、医局の最高権力者・赤石教授に、三人の研修医の指導を指示される。彼らを入局させれば、念願の心臓外科医への道が開けるが、失敗すれば…。さらに、赤石が論文データを捏造したと告発する怪文書が出回り、祐介は「犯人探し」を命じられる。個性的な研修医達の指導をし、告発の真相を探るなか、怪文書が巻き起こした騒動は、やがて予想もしなかった事態へと発展していく―。
いい加減みんなも気付き始めたであろう知念実希人である。何に気づいているのかは、詳しく書かないようにしよう。
現役医師にしてベストセラー作家という、人から嫌われる要素満点だけど、大賞を受賞して世間を黙らせられるか。(←お前が黙れ)
熱帯
汝にかかわりなきことを語るなかれ――。そんな謎めいた警句から始まる一冊の本『熱帯』。
この本に惹かれ、探し求める作家の森見登美彦氏はある日、奇妙な催し「沈黙読書会」でこの本の秘密を知る女性と出会う。そこで彼女が口にしたセリフ「この本を最後まで読んだ人間はいないんです」、この言葉の真意とは?
秘密を解き明かすべく集結した「学団」メンバーに神出鬼没の古本屋台「暴夜書房」、鍵を握る飴色のカードボックスと「部屋の中の部屋」……
幻の本をめぐる冒険はいつしか妄想の大海原を駆けめぐり、謎の源流へ!我ながら呆れるような怪作である――森見登美彦
自身の最高傑作である『夜は短し歩けよ乙女』で惜しくも大賞を逃してから、なんとなく失速気味のモリミーである。
自分でも呆れてしまうような作品は、大賞に相応しい内容だと期待したい。( ←何を偉そうに)
そして、バトンは渡された
たくさんの〈親〉たちにリレーされて育った優子。数奇な運命をたどったけど全然不幸じゃなかった少女の物語。
私には父親が三人、母親が二人いる。家族の形態は、十七年間で七回も変わった。これだけ状況が変化していれば、しんどい思いをしたこともある。新しい父親や母親に緊張したり、その家のルールに順応するのに混乱したり、せっかくなじんだ人と別れるのに切なくなったり。(本文より)
幼くして実の母親を亡くし、様々な事情で血の繋がらない〈親〉たちの間をリレーされ、四回も苗字が変わった優子だが、決して不幸だったわけではない!
〈親〉たちの愛を一身にうけて、〈親〉たちのことも愛して、いま十七歳の優子は幸せなのだ。身近な人が愛おしくなる、著者会心の感動作!
名作駅伝小説『あと少し、もう少し』の瀬尾まいこである。めっちゃファンなので、遂にノミネートされて嬉しい限りだ。こういう作家推しも楽しめるのが、賞レースのいいところだ。
『あと少し、もう少し』は最高に面白かったが、果たして面白さのバトンは受け継がれているのだろうか。( ←上手いこと言ったった、みたいな顔すんな)
さざなみのよる
小国ナスミ、享年43歳。息をひきとった瞬間から、その死は湖に落ちた雫の波紋のように、家族や友人、知人へと広がっていく。命のまばゆいきらめきを描く著者5年ぶりの感動と祝福の物語!
脚本家出身で夫婦の連名ペンネームという非常に珍しい作家、木皿泉である。
前作の『昨日のカレー、明日のパン』はデビュー作でいきなりの本屋大賞2位を獲得した。
ここで大賞を受賞し、一発屋の汚名を返上できるだろうか。(←誰もそんなこと言ってない)
ある男
愛したはずの夫は、まったくの別人であった。
「マチネの終わりに」から2年。平野啓一郎の新たなる代表作!弁護士の城戸は、かつての依頼者である里枝から、「ある男」についての奇妙な相談を受ける。
宮崎に住んでいる里枝には、2歳の次男を脳腫瘍で失って、夫と別れた過去があった。長男を引き取って14年ぶりに故郷に戻ったあと、「大祐」と再婚して、新しく生まれた女の子と4人で幸せな家庭を築いていた。ある日突然、「大祐」は、事故で命を落とす。悲しみにうちひしがれた一家に「大祐」が全くの別人だったという衝撃の事実がもたらされる……。
里枝が頼れるのは、弁護士の城戸だけだった。人はなぜ人を愛するのか。幼少期に深い傷を背負っても、人は愛にたどりつけるのか。
「大祐」の人生を探るうちに、過去を変えて生きる男たちの姿が浮かびあがる。
人間存在の根源と、この世界の真実に触れる文学作品。
デビュー以来、小説の可能性を追求する野心的な作品を多く発表している平野啓一郎。
今作では人間の内側に深く潜り込み、 その正体をあぶり出そうと試みている。
純文学の初受賞なるか。(←純文学の意味は知りません)
ひと
店を開くも失敗、交通事故死した調理師だった父。女手ひとつ、学食で働きながら東京の私大に進ませてくれた母。―その母が急死した。柏木聖輔は二十歳の秋、たった一人になった。全財産は百五十万円、奨学金を返せる自信はなく、大学は中退。仕事を探さなければと思いつつ、動き出せない日々が続いた。そんなある日、空腹に負けて吸い寄せられた商店街の惣菜屋で、買おうとしていた最後のコロッケを見知らぬお婆さんに譲った。それが運命を変えるとも知らずに……。
タイトルがシンプル過ぎてネットで検索するときに悩む作品。直球のタイトルは作品の完成度に対する自信の表れだろうか。レビューを読む限り、爽やかな青春小説らしいが…。
青春というみんなが大好きな要素は、素直に大賞に受け入れてもらえるだろうか。(←皮肉を書かないと気がすまないのか)
愛なき世界
恋のライバルが、人類だとは限らない――!? 洋食屋の見習い・藤丸陽太は、植物学研究者をめざす本村紗英に恋をした。しかし本村は、三度の飯よりシロイヌナズナ(葉っぱ)の研究が好き。見た目が殺し屋のような教授、イモに惚れ込む老教授、サボテンを巨大化させる後輩男子など、愛おしい変わり者たちと地道な研究に情熱を燃やす日々……人生のすべてを植物に捧げる本村に、藤丸は恋の光合成を起こせるのか!? 道端の草も人間も、必死に生きている。世界の隅っこが輝きだす傑作長篇。
こちらも本屋大賞のレギュラー、三浦しをん。まあハズレがない作家である。
今回もあらすじを読むだけで「こりゃ大丈夫そうだな」という感じである。さすが。
本屋大賞ノミネートレギュラーの立ち位置を、今回の大賞受賞で盤石にできるか。 (←レギュラーって、盤石の意味でもあるのでは?)
~~~
さてさて、ここからは私の本気の予想になる。
前回の2018年本屋大賞を予想したときも書いたが、本の面白さなんてのは、読むタイミングで簡単に変わる。どんなにクソみたいな小説だって、無人島で読めば面白くなるはずだ。なにしろ無人島に持っていってる時点で、「無人島に持っていく一冊」になるのだ。よく聞くでしょ。そういうやつ。うん、ちょっと意味は違うかもしれないが、大丈夫だ。
ということで、ここで予想しているランキングは、面白さ云々のランキングではなく、あくまでも「これまでの傾向からすると、こういうふうになるのが妥当だよね?」という程度のものである。そうなのだ、普通に読む価値がないレベルの記事である。
どうか賢明な皆さんは、こんな下らない記事を読んで時間を無駄にせず、将来の日本でも悲観しながら絶望してもらうなど、建設的な時間を過ごしてもらいたい。
では、ここから先は妄想じみた予想である。
行ってみよう。
スポンサーリンク
予想ランキング発表
さて、ではまずは10位である。
10作品ある中の10位となると、まるで「クソ面白くない小説」と認定されてしまいがちだが、それは違う。「2018年に発表された小説の中で10番目に面白かった小説」という意味なのだ。
だからみんなもっと評価しよう。10位を讃えよう。
ということで、みんなが讃えてくれるみたいなので、私は遠慮なく暴言を吐かせてもらう。
10位はこちら。
『ひとつむぎの手』
もうね、これ以外考えられない。
いい加減知念実希人には騙されないでしょ。色んな意味で。
売れるから書店に並べられてるだけど、本当のこの人の作品のファンって、日本に一人もいないんじゃないだろうか。
だが、私はいち読書マニアとして、知念実希人は偉い作家だと評価している。
なにせ作家としての大前提である「作品を上梓する」をコンスタントに行なっているからだ。この世には摩訶不思議な「作品を書かない作家」というものが存在していることを考えると、彼は非常に出版界にとってありがたい存在なのだ。
なのでいくら知念実希人がつまらない小説を書こうが私はまったく非難しない。むしろ褒め称える。彼の作品を、ではなく彼の姿勢を、である。
ベストセラー作家がいれば新しい作家を掘り出すのに金が使えるようになる。これからも知念実希人にはザクザクと稼いで、知念実希人よりも面白い小説を書く作家を生み出す礎になっていただきたい。頑張れ。
どうも余計なことを書きすぎた感があるが、まあいいだろう。
店頭でよく平積みされていて話題になりやすい知念実希人だが、それだけに一過性の客しか手に取らないように思う。さきほども書いたが、熱烈なファンを生み出せるタイプの作家ではないのだ。
このあとのランキングでも重要になってくるが、本屋大賞を取るために一番大事なのは、「書店員に1位と投票してもらうこと」である。
その点、熱烈なファンを持たない知念実希人は、1位に推す書店員がゼロなので、当然ランキングでも最下位になってしかるべきなのである。
ただ繰り返すが、本当に彼の存在は今の出版界にとって宝である。油田である。
どうかこのまま売れ続けてほしいと、素直に願っている。
ということで、知念実希人の『ひとつむぎの手』 は10位で。
では続いて9位の発表である。
9位は…こいつだ!
『ある男』
うーん、これはですなぁ、ちょっと『ひと』と迷ったが、色んな要素を加味して決めた次第である。
ツイッターを活用していることもあり、色んな方面で有名な平野啓一郎だが、基本畑は純文学である。だから必然的にランキングが下になる。
純文学の何が悪い、という話ではない。単純に純文学はマニアが楽しむものなのだ。しかも”どマニアの”だ。変態中の変態が楽しめる世界。それが純文学なのである。異論はまったく受け付けない。これは真実だ。
トリッキーな視覚描写で読者を魅了するのも面白いのだが、やはりそれもエンタメというよりも、「読書好きのための内輪受け」に取れてしまうことだろう。分かる人にしかウケない、というやつだ。
あらすじを読む限り、テーマは重めで硬い印象を受ける。重い作品は、楽しもうとする人にとっては確実な印象を残す。読み応えがある作品になる。
しかしながら、お祭り騒ぎされることはないだろう。ずっしりと、心の奥深くで静かに興奮して評価するものだと思う。「これが1位だ!」みたいな表面の薄っぺらい勧め方は似つかわしくない。
あと、タイトルも地味で万人受けする要素が見当たらない。元々興味のある人が手に取る本だと思う。
作品の良し悪しというよりも、本屋大賞というポップでエンタメ性の高い賞レースには合っていない、というだけである。
以上の理由から9位は『ある男』で。
さーて、酷評ばかりで若干引いている人もいるかもしれないが、気にしないでどんどん行こう。
続いては第8位である。
じゃじゃん。
『ひと』
この作品の最大のウィークポイントはタイトルである。
まずないでしょ。「2019年本屋大賞は…『ひと』です!!」とか。地味すぎる。
あと最下位の『ひとつむぎの手』と若干被ってるのも、貰い事故的に評価を下げると思う。←適当すぎ
私は未読の作家さんなのだが、経歴を見る限りかなり長いこと作家活動をされていて、作品も多数上梓されている。ということは、ファンの数も一定数いるのかもしれない。もしそうなのであれば、ある程度のポイントは期待できることだろう。
しかしながら、やはりこういった賞レースで「これが1位だ」と推すためには、それなりの理由がなければならない。
アマゾンのレビューを見る限り、『ひと』は感動作品に分類されるみたいだ。キレイなもので作られたフィクション、という印象を受けた。
これも弱い、と思う。
感動モノは根強い人気がある。むしろ感動要素がなければ売れないぐらいのレベルで、日本人は感動好きだ。そもそも物語は感動というか、昇華(止揚)がキモになることが多いので、感動方向に行くのは当然とも言えるだろう。
だが、感動させるためにキレイなものだけを集めても、なぜか感動が薄くなる、という逆転現象が起こる。
キレイなものを作るのは、ある意味フィクションの役割だと思う。普段我々が触れている世界とは違う、フィクションだからこそ生み出せるキレイな世界。大人のためのメルヘンである。
前回ノミネートした『百貨の魔法』がこれに当たる。これもやはり感動が“弱い”と感じてしまった作品だった。
感動させようと思ったら、共感が必須である。気持ちのよいものだけで作られた世界よりも、もっと血肉の通った、自分たちのような存在がそこにいないと、入り込めないのだ。
読者が求めるのは、作られた「ひと」ではなく、自分たちを重ねられるぐらい存在感を持った「人」なんじゃないだろうか。
とまあ、未読の状態でよくもまあこんだけ適当なことが書けるもんだと、我ながら呆れるが、以上の理由から『ひと』は8位で。
さてさて、続いては第7位である。まだまだ酷評は続くのだろうか…。
じゃじゃん。
『さざなみのよる』
こちらの作品も明確に弱点が存在する。
私はまったく知らないのだが、どうやら元々NHKで放送されていたドラマを小説化したものというか、スピンオフというか、メディアミックスというか、とにかくこれ単体では機能しきっていない作品なのである。そりゃダメじゃ。
いくら感動作とか言われても、元が分からなければ感動しようがない。知らないキャラクターが死んでも何も感じないのである。
作者の木皿泉は前作にしてデビュー作の『昨夜のカレー、明日のパン』でいきなり本屋大賞第2位を獲得した。ファン数が結果を大きく左右する本屋大賞でこれは、かなりの快挙だろう。
だがそれ以降、作品は発表されていない。期待していたファンも多かっただろうに、いつまでも待たされたら、興味が失せるというものである。
で、5年待たされての今作である。これはもうハードルが上がりまくりである。どれほどのもんじゃい、と思うのが人情だ。
それが、どうやらテレビドラマと連動しているらしい…。ページ数が150ちょいなんていう少なすぎるボリューム…。読み取れる情報が少なすぎるあらすじ…。
うーん、これはしょっぱいなぁ…。
あと短編集ってのも評価されにくい。評価はされても、1位にはなれないのが短編である。どうしてもライトな感想になりがちだから、短編って。しかもページ数が少ないから尚更だろう。そこまでのインパクトを読者に残せない気がする。
ということで、しょっぱい感じの『さざなみのよる』は7位で。
さあ、続いては第6位である。
これでやっと前半戦終了である。物凄い文量になってるけど、ついてこれてる人なんているのか。
では第6位の発表。
これだっ!
『熱帯』
これもまた非常に悩ましい作品である。
いや、どうやって評価しようかという意味で悩むのではなく、何位にしようか悩むのである。あらすじを読む限りはかなり面白そうだ。
分かる人もいるかもしれないが、私のこの文章は思いっきりモリミーに感化されている。パクリレベルだと自認している。本当に申し訳ない。
そんな模倣しちゃうぐらい大好きな作家の作品なので、絶対に高評価を与えたい。それがファン心理として当然なのだろう。
だが、私は厳しいファンである。作家の怠慢を許さない。適当な仕事にはちゃんとNOと言う。金を出してちゃんと作品を買っているからこそ、声を大にして「不満足です」と言う。
で、今回の『熱帯』である。もちろん未読だ。だが、なんか見える。レビューとかを眺めるだけで伝わってくるものがある。モリミーの悪癖「筆が滑りすぎて、話の筋を見失う」である。
この傾向は『聖なる怠け者の冒険』 辺りから非常に顕著になっていて、読み終わってもあまりのとっ散らかりぶりに「はあ?」となってしまうのだ。もっと嫌な言い方をすると、作品が雑なのだ。だから読者もちゃんと愛せない。愛すだけの受け皿が作品に備わっていない。
というような私の考えはまったく見当違いである可能性もある。普通にモリミーが本気を出した結果、読者を置いてけぼりにしているだけかもしれない。
というのも、モリミーは実はめちゃくちゃ賢い。だてに京都大学を無駄に卒業していない。無駄だったかだどうかは知らんが。
おふざけモリミーはとっても大衆ウケするベストセラー作家だが、本気を出した文学モリミーは一般世間の感覚からは遥か遠くの存在なのである。
デビュー作の『太陽の塔』も本来であれば、タイトルは『太陽の塔 / ピレネーの城』だった。
太陽の塔はかなり大衆レベルのタイトルだが、ピレネーの城はちょっと遠い。でもそれをタイトルに持ってきてしまう。ここにモリミーのすべてが出ているように感じる。
レビューを見る限り、『熱帯』は過去の名作たちの隠喩を含んだような表現を使っているらしい。でも教養のない人にはなんのこっちゃである。完全に置いてけぼりだ。
そんな作品が高く評価されるだろうか。
ましてや『熱帯』という地味タイトルである。装丁もイマイチだ。これは売れない。大人しく中村佑介に描いてもらえばいいものを…。
ということで、イチャモンだらけだが第6位は、森見登美彦の『熱帯』で。
スポンサーリンク
さあさあ、この時点で1万文字を超えてるわけだが、全然終わる気配がない。読んでいる人はウンザリしているだろうが、私は楽しくて仕方ない。本当にすみません。
では続いて後半戦、第5位の発表である。
第5位は~…
『火のないところに煙は』
さっきも書いたが、これはめちゃくちゃ面白そうだし、あらすじも魅力的すぎるのだが、残念ながら地雷である。悲しいけれどこれは事実だ(←断言してるこの人、未読です)。
地雷は評価できない。地雷を評価してしまったら、人としていろいろと終わってる。だから5位。それでも5位なのは面白そうだから。この“美味しそうな雰囲気”だけでポイントを獲得するだろうと予想されるから。
たまにいるのだ。思考力がほとんどないせいで、どんな駄作を読んでも「感動作!」と帯に書かれているだけで、本当に感動しちゃう輩が。アホちゃんである。別の言い方をすると、とっても幸せな人だ。こんな妄想記事を狂ったように書き殴っている私も幸せな人である。ピース。
で、だ。
これまでの本屋大賞の傾向を見ても、「面白いor面白くない」という評価基準の他に「売れるor売れない」という基準があることが分かる。そういう意味では完全に『火のないところに煙は』は売れる。売れちゃう作品である。
なので、完全に地雷(2018年で言うと『屍人荘の殺人』)だけど、それなりの順位になると予想した。
あと、本屋大賞で評価されやすい“陽”の作品でないことも、評価が低くなる一因になると思う。(そのせいで2018年は『盤上の向日葵』が大賞を獲れなかった)読後感の良さを、作品の良さと混同してしまう人も、非常に多いからだ。
大体にして「暗黒ミステリ!!」が大賞になるはずがあるまい。
ということで、『火のないところに煙は』は5位で。
…なんて書きながら「実は超面白い作品だった」という裏切りを期待している私であった。
さあどんどん行こう。
続いては、第4位!
こいつだっ!
『ベルリンは晴れているか』
これは装丁を見たときにピンと来るものがあった。上位に食い込んでくる本っぽい感じが出てた。タイトルも洒落てるし。大賞にしても栄えると思う。
歴史モノであるが、これがなかなか根強い人気がある。マイナージャンルだが、マイナーがゆえに強い。マニアはしぶといのだ。
で、題材的にも日本人はやたらとドイツ好きである。しょっちゅうドイツの話をしてる。であればベルリンの天気の話だってするだろうし、晴れてるかどうかなんて常識かもしれない。
過去の作品たちを見ても、歴史モノはしっかりと爪痕を残している。『ベルリンは晴れているか』も期待できそうである。
ただ、ちょっと気になるのは、作者の作品数の少なさである。
さっきも書いたが、本屋大賞はファンの多さが鍵になる。
作品数が少ないのであれば、ファンになりようがない。遅筆だけどファンの多い作家もいるにはいるが、それだけのインパクト残しているからである。中西智明なんかその代表例だろう。基本、遅筆の作家は忘れ去られるのが世の常である。
大賞を受賞している作家はもとから人気がある。これは動かしがたい事実である。
ということで、面白けれど、ちゃんと評価してくれる人(盲目的に推してくれる人)が少ないために、『ベルリンは晴れているか』は4位で。
さあこのクソ長い記事も佳境のベスト3である。
正直、この辺りまで来るとまったく自信がない。っていうか、今までも結構自信ない。断言しまくってきたけど、振り返ると見当違いなことを書きまくっている気がしてきた。
だがもう書いてしまったことだ。私は推敲しないことを誇りにしているブロガーである。一度書いたことはタイプミスでも平気でアップしていくスタイルである。このまま突っ走ろうじゃないか。どうせ誰もこんな最後まで読んでないだろうし。
ということで、私だけのためのベスト3の発表である。
第3位は…こいつだ!
『そして、バトンは渡された』
これはねぇ…本当に残念。
大好きな作家さんで、しかもかなり良さそうな作品だから余計に残念。もっと上位にしてあげたかった、というかむしろ1位にもなれた作品だと思ってる。
でも1位じゃなくて、3位。絶対に3位。超甘めに見ても3位。これは絶対。私には分かる。なぜなら確固たる理由があるからだ。
もしかしたら皆さんも分かっているかもしれない。
そう。
これだ。
なにこれ?
私はこの装丁を初めてみたときに思った。
制作途中…?
ダサすぎない…?
マジでこれで売る気なの?
出版社の人、みんな確認した?
こんな感じで疑問符が止まらなかった。疑問符の使用回数に限度がなくてよかった。一生分の疑問符使い果たすところだった。
こんな暗い緑の装丁が大賞に選ばれるワケがない。もし選ばれるんだとしたら、中身が他の作品よりも抜きん出ている場合のみである。過去の名作たちに並ぶレベルの。
しかし、そこまでの名作ではどうやらなさそうである。
はっきり言って、装丁と中身は関係ない。
それはライトノベルみたいな本の場合だけである。制作側が読者の想像力をアシストするときに使う場合だ。
こういった文芸書の場合、装丁はあくまでも装飾であり、本質ではない。作品の面白さにはまったく影響を与えない。
だがしかし。これは賞レースである。大賞を受賞した作品は、書店の店頭にずらずらと並べられるのだ。『そして、バトンは渡された』を並べたら、ものすっごい地味な絵面になる。売上にも影響が出ることだろう。これは書店員には推しづらい。商売人の人情である。
ということで、『そして、バトンは渡された』は3位である。
では2位を発表しよう。これで1位も確定である。
それでは…第2位!こいつだ!!!
『フーガはユーガ』
わー…パチパチ…。
出ました、面白い本の創造主伊坂幸太郎。しかし惜しくも2位である。
まず言い切っておきたいのは、伊坂幸太郎はもう大賞を受賞しない、ということだ。
これは伊坂ファンの私としては残念極まりないのだが、事実だから仕方ないだろう。
伊坂ファンであれば分かると思うが、伊坂幸太郎が書いた、という時点で面白さは保証されているようなものである。
未読だが『フーガはユーガ』も絶対に面白い。逆地雷作品である。面白そうだな…と思わせておいて裏切るのが地雷作品だが、伊坂の場合は期待させておいて、ちゃんと期待に応えるのだ。偉すぎる。
なのに誰もその偉さに気付かないor当たり前になりすぎている、ってのは酷すぎませんか。なんなら毎年本屋大賞を上げたいぐらいのレベルなのに、みんなが伊坂作品に慣れすぎてるせいで、存分に楽しんでおいて「あー面白かったー。でもいつもの伊坂だな。」で終わりである。酷すぎる。都合のいい女扱いされてる。伊坂、私はちゃんと評価してるぞ。お前は本当に偉い。偉すぎる。だから早く次の本。ね、分かるでしょ?早く書いてね。
ということで、伊坂はまったく悪くないけれど、伊坂に慣れきった読者たちのせいで2位である。もちろん私もまったく悪くない。事実を反映したまでである。
ああ、そうそう。もうひとつ、この作品の減点ポイントがあった。
タイトルである。タイトルがダメ、ということではなくて、本屋大賞の傾向として、固有名詞を使ったタイトルは敬遠されがちである。
『とっぴんぱらりの風太郎』とか『ツバキ文具店』とか『栞子さん』とか。まあビブリアがそもそもがダメだけど。
固有名詞を使っている時点で、間口を狭めてしまっているから、惜しいと思う。
ということで、堂々の2位は『フーガはユーガ』で。
さて、もう皆さんお分かりだと思うが、1位を発表させてもらう。
2019年本屋大賞を受賞するのは、こいつだっ!!!
『愛なき世界』!!!
パチパチパチ…
三浦しをん、やったね。2012年で『舟を編む』で大賞獲得して以来の2回目。本当におめでとうございます。←完全に決まったものとして進行中でございます。錯乱しているわけではありません。
今回の10作品を見たときにすぐに思ったね。8割方『愛なき世界』だな、と。
まず作者の知名度。これは申し分ない。ファンもたくさんいるし、作風的にも本屋大賞向けなポップでエンタメ性が高い。装丁も綺麗だから平積みにも耐えられる。うん、いいところづくめだ。これは書店員が推せるだろう。
それにこの『愛なき世界』、あらすじを読む限り、かなり『舟を編む』のパターンを踏襲してるっぽい。つまりは「変人に愛を。不器用な人間に光を」ってやつ。 みんな好きだよね、このパターン。
こういう「ダメだけどちゃんと幸せになって、報われる」みたいなパターンが、最近のエンタメのひとつの雛形になりつつあって、これってやっぱりスポットライトが当てられないところで鬱屈としている人が多いからなんだろうか。主人公を見ても劣等感を感じずにいられるから好まれるんだろうか。
という勘ぐりは置いておくとして。
『愛なき世界』が今回の本屋大賞で一番優れている点は、なによりも「良さが分かりやすい」という点だと思う。
まだ読んでないからはっきりとは言えないが、きっとマンガ的な分かりやすさがあるのだろう。
個性的なキャラクター。はっきりとした展開のストーリー。誰もが納得する結末。
読んだ人が誰かに勧めたいと思ったときに、「これはこういう作品なんです」と簡単に言語化できる要素がある。それが他の作品よりも顕著だと思う。
なので逆に言うと、面白さが簡単に表現できない作品は、本屋大賞では大賞までは届かない、ということ。
どれだけ面白くても、評価を下す書店員の中でも面白さが分解できなければ、1位にはできない。または1位にする人が減るだろう。個人的に2017年の森絵都の『みかづき』はそれが原因で負けたと思っている。
これを1位にしてしまうのは、無難すぎてなんだか申し訳ないのだが、こちとら本気で当てに行ってるので許してやってほしい。というかなんで私が許してもらわなけりゃならんのじゃ。逆に私が許す。みんな請え、許しを。
ということで、負け要素が一番少ないであろう『愛なき世界』が2019年本屋大賞である。
いやー、疲れた…。もう一文字も入力したくない。でも頑張っただけの変態記事には仕上がっていると思う。
以上。本家の発表を待とう。お付き合いいただき感謝。
参考までに前回の予想記事はこちら。
読書中毒ブロガーひろたつが、生涯をかけて集めた超面白い小説たちはこちら。⇒【2019年版】小説中毒が厳選した最高に面白い小説98選