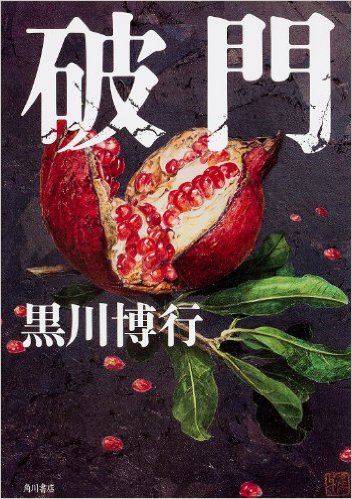
どうも。小説中毒のひろたつです。
今回は黒川博行の直木賞受賞作をご紹介したい。スピード感に溢れた最高に楽しめる、ちょっといじわるな作品である。
内容紹介
| 破門 (角川文庫) | ||||
|
「わしのケジメは金や。あの爺には金で始末をつけさせる」映画製作への出資金を持ち逃げされた、ヤクザの桑原と建設コンサルタントの二宮。失踪したプロデューサーを追い、桑原は邪魔なゴロツキを病院送りにするが、なんと相手は本家筋の構成員だった。禁忌を犯した桑原は、組同士の込みあいとなった修羅場で、生き残りを賭けた大勝負に出るが―。直木賞受賞作にして、エンターテインメント小説の最高峰「疫病神」シリーズ!
実は初の「疫病神」シリーズだった私。内容に付いて行けなかったらどうしようかと心配したが、何の問題も無かった。最高に楽しませてもらった。
それにしてもこの方、『破門』で直木賞を受賞するまで6回もノミネートしてたのか…。受賞まで18年も掛かっているとは、いやはやご苦労様でした。
スポンサーリンク
出だしでつかんでくる
何の予備知識もなしに読んだので(直木賞受賞作ということさえ、あとから知った)、完全に受け身の状態だった。物語がどの方向に進むのかも分からないし、シリーズもののキャラクターも全然分からない。物語のシリアス具合いも分からないので、かなり慎重に読ませてもらった。
しかし、読み始めてすぐに分かった。
主人公のクズ人間二宮と、根っからの極道桑原の掛け合いがこの作品の肝なのだと。
何とか平穏に暮らしたいが、性根が腐っているのでまともな生活を送れない二宮が、津に周囲に問題しか起こさない桑原に振り回される様子が、どうしようもなく痛快なのだ。
この世に数ある小説の中から当たりを引いた感覚があった。
「これは楽しめそうだな」と。
最初から面白い作品は少ない
実はこれほど小説狂いの私でも、新しい小説に手を伸ばすときや、最初の1ページ目を開くとき、「面倒だな」と感じる。なんでもそうだが、始めるときというのはエネルギーを使うものなのだ。
それに物語の場合、これからどんなふうに展開して行くかも分からないし、そもそも期待していいのかどうかさえ分からない。読者は半信半疑なのだ。そんな状態で読み始めた読者の心を最初からつかめる作品というのはかなり少ない。
そのため、作者はあの手この手で読者の興味を引こうとする。カットバックしてみたり、突拍子もないシーンから始めてみたり(伊坂幸太郎が得意とする)、いきなり会話文を差し込んだり、渾身の一文を放り込んでみたり(「さびしさは鳴る」とか)、である。
ところがどうだろうか、『破門』では力技も力技。キャラクターから湧き出る言葉たちで一気に読者の興味を掻っ攫っていくのだ。
ご都合主義一切なし
また、『破門』を読んでいて特に感じたのが、「物語らくしない」というものである。
別に悪い意味ではない。作り物感がないのだ。かと言って、リアリティがあるかと言うと、そういう意味でもない。
作品の進み方が、とても自然、とでも言えばいいのだろうか。
『破門』は主人公二宮の視点だけで進んでいくが、物語自体を回しているのは“疫病神”こと桑原である。異常なまでの腕っ節の強さがあり、しかも計算高いというチート的存在である。
しかし桑原が出てくれば解決してしまう、というようなご都合主義は一切ない。無敵の桑原が状況に苦しめられ、あがく様子がことごとく描かれている。当然、一緒にいる主人公も苦しむことになる。
これが素晴らしいと思う。
キャラクターの思惑でしか進まない
大抵の物語では、運良く仲間が助けに来たり、物語的伏線でどうにかなったりしてしまうものだが、それは言い換えるならば甘えである。フィクションの力を借りて奇跡を起こしているだけだ。キャラクターの力を越えてしまっている。ときに、キャラクターが物語のために存在してしまっているようなときもある。
しかし『破門』では、すべての行動がキャラクターの意思に基いている。誰もが保身ばかりを考え、物語の行方なんかまったく気にしていない。それぞれの思惑をなんの衒いもなく出してくる。
ストーリーのためにキャラクターがいるのではなく、キャラクターたちのうえに物語があるのが『破門』なのだ。お分かりだろうか。
スポンサーリンク
だからこそスピード感が出る
その結果どうなるか。作品のスピードが圧倒的に加速するのだ。
なにせキャラクターたちはみな必死だ。金のため、名誉のため、面子のため、そして自分の命のために、頭を使い走り回る。
そこにはストーリーではなく、全力で生きる人間たちがいるのだ。その熱量は読者にも感染する。キャラクターたちの行動がそのまま作品のスピード感に繋がるのだ。
「どうするんだ?絶体絶命じゃないか」
そんなことを本気で思わされてしまう。
これが単なるよく出来た物語であれば、「どうせ何とかなっちゃうんでしょ。伏線を回収しちゃうんでしょ」とタカをくくってしまう。読者は物語に甘えてしまう。
しかし『破門』は違う。キャラクターたちは本当にピンチに陥ってしまうし、ストーリーが味方になってくれる気配がまったくないのだ。大体にして、タイトルの『破門』からして不穏である。
ちなみに「破門」といっても組をクビになるだけではない。極道が問題を起こしてクビになった場合、自分を守ってくれる代紋がなくなってしまうので、殺されることを意味する。
全員クズの意味
『破門』で出てくるキャラクターにまともない人間はいない。極道の幹部なんかは侠気のある感じで描かれているが、そもそも極道はまともな人間ではない。
主人公もどうしようもない奴だし、桑原は完全に肉食獣である。小説という檻の中にいるから楽しめる存在だが、目の前にいたら堪ったものではない。
そんな全員クズの『破門』だが、これによってある効果が生まれる。
本来であれば主人公は読者を映し出す鏡であるべきだ。まともな一般人にしておけばいい。そうすれば作品世界により入り込ませることができる。
だが黒川博行はそうしなかった。クズに“疫病神”を取り憑かせることにした。そして、どうしようもない人間たちのどうしようもない物語を生み出した。
クズがクズであればあるほど、読者は彼らを「どうしようもねえなぁ」と見下ろすことができる。これは優越感とも似た感情だと思う。
最初はそれでいい。だけど、物語に付き合っていく内にこの優越感は、愛着に変わっていく。どうしようもないキャラクターたちを好きになってしまうのだ。
私はまんまとやられてしまった。バカだと思っていた二宮が不憫になり、そして「早く死ねばいいのに」と思っていた桑原になぜか「幸せになってほしい」と思うようになっていた。一体何なのだこの感情は。私もバカになってしまったのだろうか。
他のシリーズにも手を出したくなる
これだけキャラクターに魅了されてしまうと、どうしても他の作品にも手を出したくなるのが人情というもの。早速、一作目の『疫病神』を購入してしまった。未読なので、レビューはまた後日にでも書きたいと思う。
それにしても、キャラクターを好きにさせるというのは、作家としてはかなり有益な手法である。ファンを作れるのだから、作品を発表するごとにコンスタントに売れていくことだろう。
なんて書いてみたのだが、今、黒川博行のwikiのページを読んだところ、新卒で入った会社はすぐに辞めてるし、それ以外にやることがないというほどのギャンブル狂だし、この人、作品世界の人間そのものじゃないか。
ということは、結局は私は黒川博行という人間の魅力にやられたということなのだろうか?親交の深い東野圭吾が彼の人柄を賞賛していたのだが、そういうことなのだろうか。
やはり面白い人間には勝てないということか。
以上。
| 破門 (角川文庫) | ||||
|
こちらがシリーズ一作目。
| 疫病神 (新潮文庫) | ||||
|





