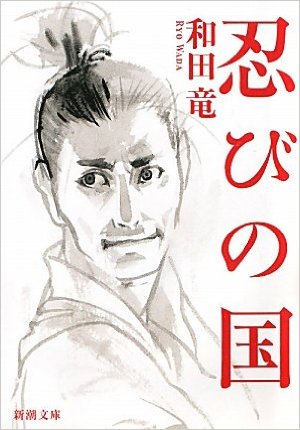
小説は読むけど時代小説は読まない人はたくさんいると思う。私も以前まではそうだった。
そんな人にうってつけの作家が和田竜である。名前は「りょう」と読むのでご注意を。坂本龍馬が由来らしい。
彼の作品は今までの時代小説とはかなり流派を離れたものになっている。それゆえに多くのファンを獲得した。(本当は山田風太郎の系譜だとは思うけど)
そんな彼の素晴らしい作品を紹介したいと思う。
内容紹介
時は戦国。忍びの無門は伊賀一の腕を誇るも無類の怠け者。女房のお国に稼ぎのなさを咎められ、百文の褒美目当てに他家の伊賀者を殺める。このとき、伊賀攻略を狙う織田信雄軍と百地三太夫率いる伊賀忍び軍団との、壮絶な戦の火蓋が切って落とされた──。破天荒な人物、スリリングな謀略、迫力の戦闘。「天正伊賀の乱」を背景に、全く新しい歴史小説の到来を宣言した圧倒的快作。
圧倒的快作とはよく言ったもので、本当に素晴らしい疾走感を味あわせてくれる作品になっている。主人公の天才忍者“無門” の瞬速に合わせて、物語もとんでもない勢いで進んでいく。時代小説にも関わらずここまで読みやすいのは、やはり和田竜の腕によるところが大きいだろう。
スポンサーリンク
キャラがたまらない
他の和田竜作品でも同様なのだが、とにかくキャラがどいつもこいつも魅力的。
主人公の無門はもちろんのこと、敵にあたる織田信雄ら武将たち。誰もに物語を用意してあるので、読者は思い入れがいがある。
というか、途中まで誰を主人公として見ていいのか分からなくなるぐらい、伊賀側と織田側を均等に描いていた。
そのせいで勝負の行方が気になって気になって仕方なかったし、何よりも誰にも負けてほしくなかった。完全に和田竜の掌である。悔しいが踊らされる。そんな作品である。
ちなみに私が一番好きなのはもちろん大膳。漫画の『キングダム』に出て来ても違和感がなさそうである。弓を放ったら、食らった相手の胴体がちぎれるんだよ?
それにしても、伊賀忍者のクズっぷりは素晴らしい。金さえ貰えれば上の人間がどうなろうとも構わないし、己の命さえも粗末にする。どうしようもないやつらなんだけど、どこか可愛げがある。やはりバカは可愛いのだ。
忍術がたまらない
またこの作品は伊賀の忍者が大量に出てくることもあり、忍術のオンパレードである。いわゆる漫画的な忍術もあれば、もっと実践的な忍術もある。
作中で使用される「人の心の操る本来の忍術」があるのだが、これは言うならば権謀術策であり、戦の醍醐味だと私は思っている。何千人もの命を己の言葉や態度ひとつで奪い去る姿は、不謹慎ながらたまらなく面白いし興奮するもの。
くだらない術から非常に高等なものまで、それぞれに大層な名前が付いているのも面白い。ただ単に小声で話すだけのことを「葉擦れの術」と呼んだりとかね。(葉が擦れている程度の音しか聞こえないため)
映像が描けている
和田竜の小説がこんなにも多くの人に受け入れられる理由のひとつに、「画をイメージしやすいこと」が挙げられる。
これは小説にとって非常に大事な要素だ。
なんてったって、小説は紙に文字を書いただけの媒体である。ライトノベルであれば少しは絵を入れたりできるが、小説の場合は完全に読者の想像力に依存している。読者がしっかりと頭を使ってくれないと作品として浮き上がってこない。
脚本家もである和田竜はそこを工夫している。彼の頭の中にあるイメージを的確に読者に伝えられるのだ。
例えば、『忍びの国』でも特に垂涎の戦闘シーンを見てみると、読んでいる最中はあまりのスピード感と興奮にさらっと読んでしまうが、あとからよく確認すると、戦闘の描写が少ないことに気付く。頭の中ではキャラたちが攻撃を繰り出し合い、しばらくの間もみ合っていたイメージだったのだが、実際はほんの何行かで終わっていた。
これはそれだけ和田竜の文章や設定が読者のイメージを喚起しやすいものだからなのだろう。漫画的なキャラの能力はこういった部分でも役立つ。漫画的だからこそ、漫画のように読者は容易に“画”を脳内に描くことができるのだ。そりゃ面白くなるさ。
スポンサーリンク
楽しめない人は…
さて、今回の記事を書くにあたって他の方のレビューを拝見させてもらったが、やはり賛否には分かれているようである。
まあどんな作品にも「つまらない」と思う人はいるし、私もこれまで数々の駄作たちの餌食になってきた。その気持ちはよく分かる。
だが低評価を付けている人たちのレビューを読む限りだと、たぶん勝手に脳内で時代小説というものをルール化しすぎていたり、先入観で縛り付けられているように感じた。
それではあまりにももったいないと思う。これだけみんなが狂喜乱舞する物語を楽しめないなんて…!
やはり物語というのは、頭の中をまっさらにして、素直な気持ちで向き合うのが一番だと思うのだ。結構、難しいけどね。
和田竜を褒めよう
和田竜は偉い。彼の小説を読むたびに本当に思う。
作品は非常に読みやすいエンタメとして確立されていて、普段歴史小説を読まないような人にも受け入れやすくしてある。ときに漫画的とも言える戦闘シーンは、さらに読者の裾野を広げている。現に私が和田竜から時代小説を読むようになった。(ちなみに次は大御所、司馬遼太郎だった)
そのせいか中には和田竜の作品を「軽い」や「リアリティ」がないという声が聞かれる。もしかしたら従来の時代小説ファンからしたらそうなのかもしれない。
だがだ。
彼の作品を読めば分かる通り、作品の裏に綿密な知識が潜んでいる。文献を漁り、想像力を限りなく働かせている。作品の面白さは担保しつつも、ちゃんとした時代劇を描こうと力を尽くしている。
そんな彼の姿勢は素晴らしいと思う。実際彼の小説は多くの人を楽しませ、支持されている。そして新たな時代小説として確立しつつある。
これからも上質な物語を生み出してくれることを期待したい。
以上。
本屋大賞を受賞した和田竜の最高傑作はこちら。





